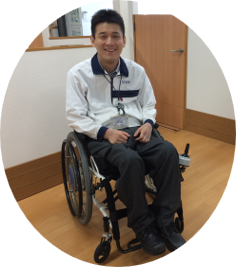積水ハウス株式会社(以下、積水ハウス)は、“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というグローバルビジョンのもと、人生100年時代にふさわしい新たな住まいの価値創出を目指しています。その実現に向け、「住」を中心に据えながら、ハード・ソフト・サービスを一体的に提供するグローバル企業への進化を加速させています。
こうした活動の一環として、展示場をはじめ、ショールームや体験型施設(Tomorrow's Life Museum)など、お客さまをお迎えする全施設において、障害のあるお客さまが安心してお越しいただける環境作りを目指し、「UD(※1)サービスハンドブック」を制作。続けて、全国の住宅展示場で「UDサービス実習」と呼ばれる実践型研修を開始し、サービス品質の向上に努めています。
今回の取り組みの背景と具体的な取り組みについて、人事総務部 障がい者雇用推進室のご担当者さまにお話をうかがいました。
※1 UD ユニバーサルデザインの略