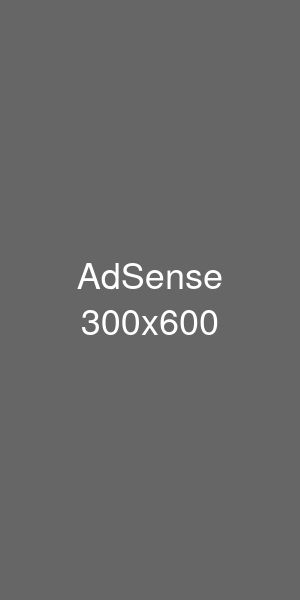視覚障害のある方が、道を歩いているときに持っている杖をご存じでしょうか?
この杖の名前を白杖(はくじょう)といいます。
白杖とは、弱視の方々や私のようなまったく目が見えない人にとっても大切なツールです。
今回は、視覚障害のある方にとって、道を歩く際になくてはならない存在である白杖についてお伝えしたいと思います。

実は白杖にはたくさん種類がある?!
見た感じただの白い杖のように思う方が多いと思いますが、実は白杖にはさまざまな種類があります。
例えば、杖の先端部分が丸くなっているもの、先端にローラーがついているもの、杖自体が折りたたみ式のものなどがあります。
また、使用する人の身長や歩く速さによって、長さも変わります。
使用する人の好み・体格によって白杖の種類が選べるのです。
ちなみに私は、とにかく軽い白杖が好みです。
このようにたくさんの種類がある白杖ですが、実際どのように使用しているのでしょうか。
ここからは、白杖の代表的な使い方についてお伝えしていきます。
白杖の使い方
白杖の使い方は大きく3つあります。
- 安全確認
- シンボル
- 音の反響
1.安全確認
自分の1歩先の地面を白杖でたたいたり地面をスライドさせることで、自分が歩く先に障害物などがないか、地面の状況や進行方向を確認します。
また、点字ブロックの上を歩く際も、足の感覚と白杖で触れた感覚を利用して歩いています。
2.シンボル
白杖を持っていることで、自分に視覚障害があることを周りの人に伝えます。
視覚障害があるといっても、見え方はさまざまです。
私のように全く見えない人もいれば、少しだけ見える人、視野が非常に狭い人など、人によって見え方は異なります。
皆さんお気づきだと思います。
白杖を持っているからといって皆が全く見えていないわけではないのです。
外を歩く際には、見え方によって周りの人に気づかずぶつかってしまう場合もあります。
こうしたことを防ぐために、白杖を持っていることでまず、周りの人に自分に視覚障害があることを伝える役割もあります。
3.音の反響
これは少し特殊な使い方です。
地面を白杖でたたくと音がします。
その音の反響を聞いて、今どれくらいの広さの場所にいるのか、入り口はどのあたりにあるのかを確認します。
当然ながら、視覚障害のある方が皆それをできるわけではありませんが、音の反響を歩く時の参考にしている人もいるのです。
白杖の種類
また、白杖の種類でも目的や個人の見え方によって異なります。
ここでは代表的な白杖の種類を3種類紹介します。
- シンボルケーン※IDケーン
- ロングケーン
- サポートケーン
1.シンボルケーン※IDケーン

主に周囲の人に自分が視覚障害者であることを知らせるために使う白杖です。
弱視の人など全盲の人に比べて歩行に支障がない人がしている白杖として知られています。形式はロングケーンと比較すると短く細い形をしています。
2.ロングケーン

ロングケーンは、歩行の際に一歩先の障害物を把握するための白杖です。
一般的に知られている白杖で、先ほどご説明した3つの仕様用途を満たしている白杖です。この白杖には、直杖と折りたたみ式があり、形状も長く、1歩先の障害物や歩行確認に向いています。
3.サポートケーン

サポートケーンは、別名身体支持杖とも呼ばれており身体を支えるための白杖です。特徴としては頑丈で柔軟姓のある材質で、グリップが柄になっている白杖になります。主に足腰の弱い方や高齢の方が使う白杖です。
街中や駅で視覚障害者を見かけた時、あなたならどうしますか?
白杖には使い方や目的、個人の見え方によってさまざまです。一概に視覚障害者だからと言って、まったく目が見えないわけではありません。それぞれ固有の見え方があります。
「街中や駅で、視覚障害のある方を見かけた時あなたならどうしますか?」
はじめて声をかけるのはとても勇気がいりますよね。
ミライロが運営するユニバーサルマナー検定は、障害のある当事者講師が講義内容を監修しており、当事者自身のエピソードや覚えやすいフレーズにより、障害者をはじめとする多様な方々と向き合うマインドやアクションを身に着けることが出来ます。
ユニバーサルマナー検定2級取得講座では、実際に皆さんに白杖を使ってもらいながら、視覚障害について学ぶことができます。
私も視覚障害者の視点を活かして講師としてお伝えしています。ご興味のある方は下記ページをご確認ください。
まとめ
このように、さまざまな用途で使用している白杖は、視覚障害者が移動する上でなくてはならない存在です。
しかし白杖があるからといって、いつでもどこでも安全に歩けるわけではありません。
白杖を使用して歩いている方は、白杖から伝わってくる地面の感覚と、周りの音を頼りにしていることが多いです。
どれだけ歩きなれている場所であっても、音が聞こえづらい環境になると、いっぺんに移動が難しくなります。
例えば、電車が通過しているときの駅のホームや、工事中の道路では周りの音が全く聞こえなくなります。
もし、白杖を使用されている方を見かけたら、その場の周りの音に注目してみてください。
普段と明らかに違う大きな音がしている場合、そっと一声かけてくださるだけで、とてもありがたいのです。
※原口が過去に執筆した「音に関する」ブログ
『視覚障害者の夏の意外な天敵とは!?~日常から気づく、外を歩く際のポイント~』はこちら