































































投資家として第一線で、7,000人もの経営者にインタビューし、企業や人の成長を見極めてきた、藤野英人さん。将来の不安を打ち破るための人生戦略として、投資家の思考を、日々の習慣に取り入れる方法を伝えています。藤野さんの投資の経験から、成長し続ける企業や個人、そしてバリアフリーとの不思議な関係性について、お話を伺いました。

1966年富山県富山市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、国内・外資大手投資運用会社でファンドマネージャーを歴任後、2003年レオス・キャピタルワークス株式会社を創業。日本の成長企業に投資する株式投資信託「ひふみ」シリーズを運用。投資教育にも注力しており、明治大学商学部兼任講師、JPXアカデミーフェローを長年務める。一般社団法人投資信託協会理事。

1989年に愛知県安城市で生まれ、岐阜県中津川市で育つ。生まれつき骨が脆く折れやすいため、車いすで生活を送る。自身の経験に基づくビジネスプランを考案し、国内で13の賞を獲得。障害を価値に変える「バリアバリュー」を提唱し、大学在学中に株式会社ミライロを設立した。高齢者や障害者など誰もが快適なユニバーサルデザインの事業を開始、障害のある当事者視点を取り入れた設計監修・製品開発・教育研修を提供する。

藤野さんは、たくさんの経営者にインタビューされていますよね。
そうですね。運用の仕事を30年してきましたので、のべ7,000人以上の経営者にお会いしました。


成功する人に共通することはありましたか?
うーん、まず結局は「運」の要素が大きいと思っています。


なるほど。私がミライロを10年続けることができたのも、運が良かったからだと思います。藤野さんとお知り合いになれたこともそうですが、偶然にもたくさんの方々とご縁をつないでもらい、応援してもらって、今があります!
こちらこそ、垣内さんに出会えたのは、運が良かったからです。でもね、短期的な成功は「運」で得られても、長期的な成功となると、それだけでは難しい。


幸せな状態を「運」だけで維持することはできないと、藤野さんは言います。維持するには、どうしたら良いのでしょうか。
一つは「感謝の気持ちを持つこと」です。成功した経営者は「運が良かった」という口グセの人が多いんですが、それはなぜかというと、感謝の気持ちがしっかりと持てているからです。


「成功したのは自分の実力だ」とふんぞり返るのではなく、謙虚な姿勢で感謝しているということですね。
身近な例を出すと、コンビニで買い物をして、レジで商品を受取る時に「ありがとう」とお礼を言えているかどうか。できる経営者ほど、お店の人にお礼を丁寧に言うのが習慣になっているんですが、全体の割合としてはすごく少ないです。


確かに、「ありがとう」と言っている人は少ないかもしれません。
でも、「ありがとう」と言うことは、自分だけでなく、日本を明るくする最大の「投資」なんですよ!


「ありがとう」と言うのは0円なのに、得られるリターンはとても大きいと、藤野さんは語ります。なぜなら、「ありがとう」と言う人は、自然と心が前向きでハッピーな状態になるからです。暗くて後ろ向きな人よりも、明るくて前向きな人の方が、ビジネスチャンスを掴みやすいそうです。
「ありがとう」と普段から言ってくれる人に対して、意地悪したり、復讐したり、ネガティブな気持ちを持ったりする人は少ないですからね。


思わず、周囲が助けたくなってしまうということですね。
それと「ありがとう」を言う人は、相手の感情や行動によく気がつくようになります。


「ありがとう」と言われた人にも、良いことがありますか?
もちろん!「ありがとう」と言ってもらった店員さんは、働くことが楽しくなるんです。コンビニのレジで、店員さんと目も合わせず、黙ってお金やカードを渡す人が多いですよね?


会話はあっても「Suica(電子マネー)で!」だけ、という人も多いですね。
お客さんが厳しいと、店員さんも辛くなる。若い人がどんどん働きたくなくなってしまうんです。働くことが楽しくない人が多くなれば、当然日本の景気は悪くなります。


未来が暗くなる、負のサイクルですね……。
お金を払ったからと言って、お客さんがエライわけじゃないですよね。店員さんはお金に見合うサービスを提供しているわけですから。対等なんですよ。


本当にそうですね。私の場合、以前は「ありがとう」よりも「すみません」と口にすることが、圧倒的に多かったんです。車いすを押してもらってすみません、道を開けてもらって申し訳ない……と。
なるほど。そういう人も多いかもしれませんね。


ある時から「ありがとう」を意識して言うようになりました。そうすると、周囲の雰囲気や向き合い方も変わったんです。

車いすの自分に手助けを申し出てくれる人に対して「ありがとう」と言う頻度を増やした垣内。少しずつ、明るく声をかけてくれることが増えました。手助けが必要ない時も「今は大丈夫です、ありがとうございます!」と言ってみると恐る恐る声をかけた人が、ホッと表情を緩めてくれることもありました。
きっかけがあると、人の行動は変わりますからね!私は「投資」の定義を、「自分のエネルギーを投入して、未来からお返しをいただくこと」と考えています。「ありがとう」と自分から言うことが、投資の第一歩だと思います。


成功する人という範囲を広げて、成功する会社に共通することはありますか?
たくさんありますが、最近気づいたのは「障害者を積極的に雇用している会社」です。


えっ!なぜそう思われたんですか?
経済産業省の「健康経営銘柄」の基準検討委員会や、「新・ダイバーシティ経営企業100選」の運営委員を務めていて、気づきました。

藤野さんが言うには、雇用している障害者の人数が全社員の2.5%を越えてくると、顕著に企業の業績が良くなるそうです。障害者が活躍している企業ほど、経済的にも成功していることに、藤野さんは気づきました。
詳しく数値を検証すると、正確な要因がわかると思いますが、少なくとも私がいくつかの企業にインタビューする上では「経営者が意識して、障害者の雇用を増やしているか?」がポイントだと思いました。


平成30年4月時点の民間企業の法定雇用率(民間企業に義務付けられた障害者の雇用率)は2.2%ですから、“ただなんとなく”雇用しているだけでは、2.5%には絶対に達しないと思います。経営者が意識しているということですね。
障害者の働きやすさを考えている企業というのは、女性や外国人の登用、環境問題への配慮なども考えているんですよ。


他者への思いやりや優しさを持つ、という意味では共通していますからね。
そういう企業は、おのずとお客さんにも真摯に向き合い、顧客満足度を上げ続けています。障害者を積極的に雇用できるというのは、経営陣のレベルの高さを表す、一種のバロメーターだと僕は思っています。


それはとても心強い考察です!
経営者や社員にインタビューすると「障害者と一緒に仕事をして、社内が明るくなった」と声が上がることも、めずらしくないですよ。


障害者と働くことで、企業にとって良い効果が現れるというケースは多いと思います。新しい気づきや発想などが生まれますから。
先日受講させてもらったユニバーサルマナー検定でも、車いすに乗っている女性がカフェで席を探している写真を見せて、「この人が困っていることはなんでしょう?」という問題があったじゃないですか?あれは新しい気づきや発想が生まれて、良い問いかけだと思いました。

高齢者や障害者への向き合い方を学ぶ、ユニバーサルマナー検定。2019年9月20日にレオス・キャピタルワークスの本社にて、垣内が講師を務め、多くの社員の皆さんが受講してくれました。藤野さんが触れたのは、ユニバーサルマナー検定3級の演習問題です。

ありがとうございます。歩いている人は、段差があることになかなか気づかないんです。でも、車いすに乗っている人と一緒に仕事をすれば、自然と気づくようになります。過ごす時間が多いだけ、視点が増えるんです。
視点が多い人というのは、ビジネスでも成功しやすい。そういう人が多い企業ほど、業績を上げるのは自然なことですね。企業だけじゃなくて、ユニバーサルマナーができている人って、モテるんじゃないかな。(笑)


デートの相手が、街中で困っている人にパッと声をかけたり、先回りしてドアを開けてあげたりしているところを見たら、スマートでカッコいいなと思いますからね。(笑)

障害者を積極的に雇用している企業が、業績を伸ばし始めている日本。障害者が働き、お金を稼いで、街へ出ていくという好循環が回り始めています。街中のバリアフリーについてはどうでしょうか。
30年ほど前、オランダのアムステルダムに出張した時、車いすに乗っている人をたくさん見かけて、驚愕したことがあります。


ちょうど僕が生まれた頃ですね。
あまりにも見かけるものだから「オランダでは、足が悪くなる病気が流行ったり、大きな事故があったりしたのかな?」って思ったくらいで。もちろん、そんなことはまったく無くて。


とすると、理由はなんだったんですか?
帰国して、福祉系の専門家に聞いてみたら「日本もオランダと同じくらい、足の悪い人はいるよ。外に出られないだけで」と。驚きましたよ!


30年前だったら、そうですね……。日本でバリアフリーが劇的に進んだのは、この20年ほどのことですから。障害者が生まれたことを近所に隠すことも、めずらしくなかった時代です。
その頃に比べたら日本のバリアフリーは、遥かに良くなったと思います。でもまだ「障害者がお金を消費できる場所」は少ないですよね?


そうなんです!公共施設や交通機関のバリアフリーは進みましたが、居酒屋、レストラン、ライブハウス、アミューズメントパークなど、余暇を楽しめる場所はまだまだ進んでいません。
ものすごく重要ですよね。だって、お金を使いたいと思うから、働きたい(稼ぎたい)と思う障害者が増えるわけじゃないですか。


お店側は「バリアフリーにしても、障害者は来ないだろう」「人数が少ないから、マーケットとして見れない」という声が、どうしても多くなってしまいますね。
それは勘違いですね。たとえば私は、最近「ゲコノミスト」というグループをSNSで立ち上げました。下戸、つまりお酒が飲めない人たちの集まりです。


ゲコノミスト!(笑) 私も下戸です!
それは勘違いですね。たとえば私は、最近「ゲコノミスト」というグループをSNSで立ち上げました。下戸、つまりお酒が飲めない人たちの集まりです。


下戸はマイノリティとして見られがちですが、実は日本に1,000万人近くいると言われています。これは巨大なマーケット「ゲコノミクス」です。


最近はノンアルコールメニューを増やす居酒屋も見かけます。ノンアルコールバーが、SNSで話題になったこともありましたね。
お酒に弱い人だけじゃなく、ドライバー下戸、妊娠下戸、ドクターストップ下戸などもいますから、需要はかなり高いんです。

下戸の人々が満足する商品や場所を提供すれば、売上があがり、産業となり、GDPも上昇すると、藤野さんは言います。下戸が生産者側になり、業界が賑わうという、日本にとって良い循環も回り始めるのです。

下戸の人数と、障害者の人数は、ほぼ同じなんですよ。障害者にとって快適で安心できる場所は、足腰の悪い高齢者にとっても同じ。これも巨大なマーケットです。
少子高齢化と言うと暗い未来を想像してしまいがちですが、大きなビジネスチャンスが眠っている市場が、日本にはたくさんあるんですよね。


障害者を食い物にするのではなく、彼らの生活を豊かにするためにサービスを提供し、企業も儲かって、豊かになる。そんな成功事例を増やしていくことが、急務だと思います。社会性と経済性の両立が重要です。

顧客の視点を持つマイノリティを積極的に採用し、しっかりと利益も上げている企業を、投資家として応援していきたいです。あとは、国が応援するというのも重要ですね。国が先端的な事例として表彰した企業は、出資を受けやすくなったり、金利が安くなったり、といった後押しができると思います。


藤野さんがおっしゃっていた、エネルギーを投資して、未来からお返しをいただく、という考え方ですね。明るい未来を作るために、私も全力で頑張ります。
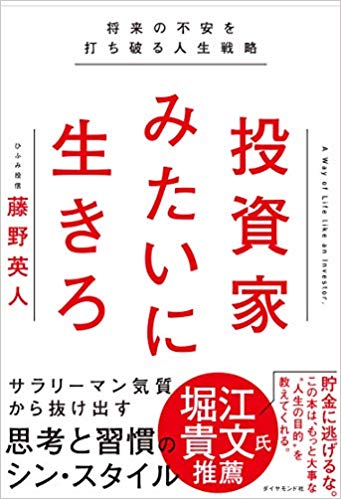
「ひふみ投信」で有名なファンドマネジャー・藤野英人さんが説く、「これからの考え方・生き方」を説いた1冊。未来に向けて「見える資産」「見えない資産」を貯めていき、市場価値を高めるにはどうすればいいのか。リスクをとって「未来からのお返し」を得る思考と習慣のすべて。


