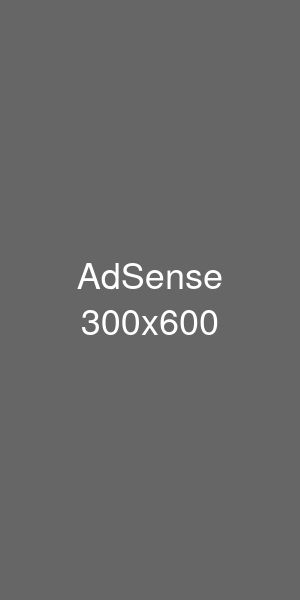【プロフィール】
株式会社ミライロ
垣内俊哉
2010年、株式会社ミライロを設立。バリアフリーマップの制作や、多様な方と向き合う「マインド」と「アクション」を学ぶユニバーサルマナー検定の運営を行う。近年はデジタル障害者手帳「ミライロID」の開発・運営も手掛けている。著書に『バリアバリュー 障害を価値に変える』(新潮社)、『10歳から知りたいバリアバリュー思考 自分の強みの見つけかた』(KADOKAWA)、『バリアバリューの経営』(東洋経済新報社)がある。
KEIPE株式会社
赤池侑馬
2017年、KEIPE(ケイプ)株式会社を設立。働くことに障害を抱えていた兄がきっかけとなり、山梨県で障害者就労支援事業の運営をスタート。近年は、福祉の枠組みを超えて、働きづらさを抱える人が地域を支えるローカルビジネスに参画できる仕組みづくりに挑戦中。現在は「課題を可能性に変える」をテーマに、飲食業、地域商社事業、資源循環事業、企業と福祉事業所のマッチング事業などを展開している。
株式会社トレジャーフット
田中祐樹
新卒で株式会社セプテーニ入社後、マーケティングの力をローカルで活かすために沖縄県へ移住。地域密着メディアを運営する株式会社パムローカルメディア代表取締役社長に就任し、地域課題の解決に奔走。その後、株式会社ベネフィット・ワンにてサービス開発部部長代理 兼 新規事業開発の責任者を経て、2018年3月に株式会社トレジャーフット設立。著書に『稼げるフリーランスの法則』(日本経済新聞出版)がある。
現代の企業経営において、「多様性(ダイバーシティ)」と「包摂(インクルージョン)」は、社会の持続可能性を支える重要な要素として注目を集めています。しかし、実際にその理念を実践し、企業文化や地域社会に根付かせることは簡単ではありません。それには、課題を一つ一つ乗り越え、組織内外の価値観を変革していく努力が必要です。
本記事では、障害者支援や地域活性化、そして新しい働き方の実現を目指して取り組む3つの企業、株式会社ミライロ、KEIPE株式会社、株式会社トレジャーフットの代表者にお話を伺いました。それぞれの企業が直面した課題や試行錯誤、そして多様性を受け入れることによって生まれた新たな可能性について深掘りします。
多様な背景や価値観を持つ人々が一緒に働くことが、いかに組織の成長や社会の進歩に寄与するのか。これからの日本社会に必要な変革のヒントを、3社の取り組みから探ります。
ーーーまず、各社の取り組みについて簡単に教えていただけますか?
垣内:「ミライロは『バリアバリュー』という企業理念を掲げて、2010年に事業をスタートしました。私は骨の病気で車いすを使っていますが、これは私の家族にも受け継がれてきたもので、明治の時代から続いています。当時は舗装された道路もなく、車いすを外で使うのは非常に困難な時代でした。今では、外に出て学ぶことや働くこともできるようになりましたが、まだ不便や障害が残っています。
私たちは、障害を『強み』として捉え、社会を変えていこうとしています。ただし、それを『武器』にしてはならないと常々社員にも伝えています。バリアフリーが重要だと言われれば誰も否定はできません。でも、そこに『これだけの人を助ける』『コスト削減につながる』という持続可能なビジネスアプローチが必要だと考えています」
赤池:「KEIPEは『働く喜びを伝える人を作る』を理念に掲げています。立ち上げのきっかけは、私の兄がバイク事故で働けなくなったことでした。その経験から、働きづらさを抱える人々が社会で新しい価値を生み出せるような活動に取り組んでいます。
例えば、農家さんの高齢化や人手不足の課題を解決する工場を立ち上げたり、廃材やフードロスを減らす取り組みをしたりしています。障害のある方々だけでなく、子育て中のお母さんや働きづらい環境にある人たちも支援の対象としています。また、山梨の農家さんとの取り組みでは、廃棄されるはずのフルーツを活用してドライフルーツやジェラートを製造・販売する工場を設立しました。こうしたローカルビジネスの成功モデルを全国に広げていきたいと考えています」
田中:「トレジャーフットは、『新しい働き方を創造し、地場産業の発展に貢献する』をミッションにしています。まもなく8期目を迎える会社です。正社員雇用だけでなく、フリーランスや副業といった多様な働き方を支援し、地域活性化を目指しています。
地方の中小企業や自治体との連携も進めており、オンラインコミュニティを活用した人材育成プログラムを運営しています。この仕組みにより、優秀な人材が地域に留まり、地産地消の経済循環を実現しています。最近では、障害者支援施設の仕事マッチング事業なども展開し、地域の活性化と新しい働き方の両立を目指しています」

穏やかな雰囲気で対談は進んだ。左から垣内、田中氏、赤池氏。
いろいろな人が働きやすい社会を目指して
ーーー皆さん共通するのが、「いろいろな人が働きやすい社会を作る」という点かと思います。ダイバーシティやインクルージョンは言葉としてはよく聞きますが、実際に取り組むとなると、様々な困難や課題があると思います。それぞれの視点から、どのように課題を発見し、それを解決してきたのか教えていただけますか?
垣内:「組織というのは本来、同質性が高いほど意思疎通が速やかでマネジメントが楽なんですよね。軍隊のような一糸乱れぬ組織がその典型ですが、時代にそぐわないというのが今のダイバーシティの機運だと思います。ただ、多様性を受け入れるというのは綺麗事だけでは続きません。哲学として根付かせることが必要です。
私は植物の『生存戦略』からヒントを得ました。例えば、引っ付き虫は種を2種類持ち、すぐに発芽するものと時間をかけて発芽するものに分けられています。これにより、除草剤や日照りなどのリスクに対応しているのです。人間も同様で、成長の仕方に正解はありません。苦手な部分は皆で補い、強みを伸ばす組織づくりが重要です。
私自身、過去に入院や心肺停止を経験しましたが、その間社員が会社を支えてくれました。この経験を通じて、社員同士が助け合い、困難な時期を乗り越える風土が少しずつ醸成されてきました。多様性を尊重する組織を作るには、5年、10年とかけて熟成していくものだと感じています」
赤池:「ダイバーシティを推進する上で、多様なバックグラウンドを持つ人々が集まる組織では、時に意見がぶつかることがあります。例えば、障害者支援の現場では、サポートが過剰になって本人の自主性を損なってしまうケースもあります。また、働き方に関する固定観念が、個人の可能性に蓋をしてしまうこともあります。
現在の社会構造は、いわゆる『強い人』が生き残る仕組みを基盤としているように感じています。特に経済が中心となる価値観の中で、障害がある人が『弱い』と定義されてしまうことが多いのではないでしょうか。しかし、別の価値観があってもいいのだという認識を広げていくことが、これからの社会にとって非常に重要だと考えています」

同質性は「取り残される人」を生み出してしまうと語るKEIPEの赤池氏。
赤池:「私自身、会社経営をする中で、同質化のメリットも感じています。ミッションやビジョンに深く共感し、同じ方向を向いているメンバーが集まると、非常に大きな力を発揮することがあります。ただ、その一方で、そうした同質性が『取り残される人』を生み出してしまうという弊害も無視できません。この点を痛感したきっかけの一つが、5月に県立美術館のレストランをオープンした際の出来事です。
そのとき、統合失調症のある方が社内から応募してくれました。正直なところ、レストランという職場において『良いサービスを提供するためにはホールに立てないのではないか』というバイアスが私自身にもあり、裏方の業務をお願いするつもりでした。しかし、オープン2週間前の朝礼で、その方が眠そうな顔をしていたので『寝れてないの?心配事でもあるの?』と尋ねたところ、彼女が『夜中まで接客のYouTubeを見て勉強しているんです』と答えました。その姿に心を打たれ、『ホールに挑戦してみよう』と決断しました。
もちろん最初はクレームもありましたし、彼女の接客は完璧とは言えませんでした。それでも、やりたいという気持ちを尊重し、まずはできる業務から始めてもらいました。業務を分解し、一つ一つのステップを丁寧に進めた結果、彼女は次第にホール全体を見渡せるようになり、適切に立ち回れるまで成長しました。この経験を通じて、自分自身のバイアスが、相手の可能性に蓋をしていたことに気づかされました。
組織としても、誰もがフラットに人と向き合い、その人が持つ可能性を信じる姿勢が重要だと感じています。そして、その過程で組織が学び、成長する。こうした体験は、現場で直接関わった人にしか実感できないことが多いです。そのため、こうした経験を共有し、共感を広げるために、同じような体験を重ねることが必要だと思っています」
体験から気づきを得る:ユニバーサルマナー検定とは?
ーーー素敵なストーリーですね。しかし、こうした「気づき」は実際に体験した人だからこそわかる部分があると思うのです。体験をする機会がない人はどのように「気づき」を得ればよいのでしょうか。

ユニバーサルマナー検定のこれまでの認定者数は
国内で23万人にのぼる、と話す垣内。
赤池:「ユニバーサルマナー検定というのを、ぜひお勧めしたいです。垣内さん、ご説明をお願いします」
垣内:「ユニバーサルマナー検定は、多様性を受け入れるための実践型研修として、2013年にスタートしました。これまでの認定者数は国内で23万人にのぼり、車いすの操作方法や視覚障害者の誘導方法といった実技から、LGBTQ+や認知症の方への理解を深める内容まで、多岐にわたるプログラムを提供しています。ユニバーサルマナー検定3級では主にコミュニケーションの基本を学び、2級では実技を含むより高度なスキルを身につけられる内容になっています。
例えば、車いすユーザーとの関わりでは『先回りして行動するのではなく、選択肢を提供する』ことの重要性を伝えています。障害者だけでなく高齢者や外国人など、異なるバックグラウンドを持つ人々に対して、個別に向き合い、その人が何を求めているかを理解する姿勢を育むことが目的です。
受講企業の中には、会長や社長をはじめとする経営陣がユニバーサルマナー検定を受講したことをきっかけに、全社的な取り組みへと広がったところもあります。同社では現在、全社員の受講とともに、全ての部署で障害者が活躍できる環境づくりを目指しています。これにより、組織内の意識が大きく変わり、多様性の受け入れが進んでいます。
また、必修授業としてユニバーサルマナー検定を導入し、学生全員が受講している大学もあります。若い世代がダイバーシティに向けた取り組みを自然に実践している一方で、30代以上の世代ではまだ意識のアップデートが必要だと感じます。障害のある子どもとそうではない子どもを切り離し、別々の環境で教育する分離教育の影響もあり、多様性を受け入れることに躊躇が見られることもあります。ユニバーサルマナー検定は、特にこうした世代にとって意識を変える有効なきっかけになると考えています。
実際、ある高校でユニバーサルマナー検定を実施したとき、1年生の生徒たちが最初は『障害者にどう声をかけたらよいか分からない』と自信のなさを口にしていました。しかし、検定受講後には自信を持って声をかけられるようになり、街中でも積極的にサポートをする様子が見られるようになりました。こうした体験型の学びを通じて、多様性を受け入れる文化がさらに広がり、多くの人が働きやすい社会が実現していくことを期待しています」

「多くの人が働きやすい社会」が実現するためのアイデアは尽きない。
お問合せ
・ミライロ 経営企画部 広報担当
E-Mail:press@mirairo.co.jp