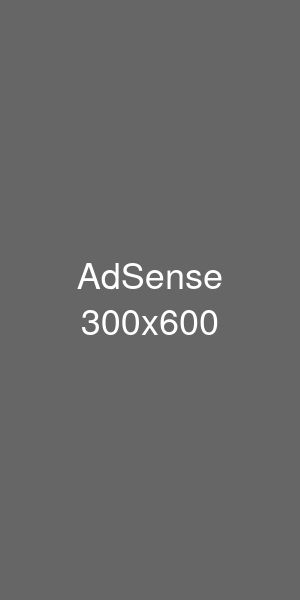【プロフィール】
株式会社ミライロ
垣内俊哉
2010年、株式会社ミライロを設立。バリアフリーマップの制作や、多様な方と向き合う「マインド」と「アクション」を学ぶユニバーサルマナー検定の運営を行う。近年はデジタル障害者手帳「ミライロID」の開発・運営も手掛けている。著書に『バリアバリュー 障害を価値に変える』(新潮社)、『10歳から知りたいバリアバリュー思考 自分の強みの見つけかた』(KADOKAWA)、『バリアバリューの経営』(東洋経済新報社)がある。
KEIPE株式会社
赤池侑馬
2017年、KEIPE(ケイプ)株式会社を設立。働くことに障害を抱えていた兄がきっかけとなり、山梨県で障害者就労支援事業の運営をスタート。近年は、福祉の枠組みを超えて、働きづらさを抱える人が地域を支えるローカルビジネスに参画できる仕組みづくりに挑戦中。現在は「課題を可能性に変える」をテーマに、飲食業、地域商社事業、資源循環事業、企業と福祉事業所のマッチング事業などを展開している。
株式会社トレジャーフット
田中祐樹
新卒で株式会社セプテーニ入社後、マーケティングの力をローカルで活かすために沖縄県へ移住。地域密着メディアを運営する株式会社パムローカルメディア代表取締役社長に就任し、地域課題の解決に奔走。その後、株式会社ベネフィット・ワンにてサービス開発部部長代理 兼 新規事業開発の責任者を経て、2018年3月に株式会社トレジャーフット設立。著書に『稼げるフリーランスの法則』(日本経済新聞出版)がある。
現代の社会や企業において、多様性(ダイバーシティ)と包摂(インクルージョン)は欠かせないテーマとなっています。しかし、理念を掲げるだけでは真の変革は起こりません。それを現実に落とし込み、文化として定着させるには、具体的な取り組みや実践が求められます。
本記事では、「体験」や「共感」を通じて、多様性を育むための工夫を重ねている3社の取り組みに迫ります。前回の記事でご紹介した 、株式会社ミライロ、KEIPE株式会社、株式会社トレジャーフットの実践事例に続き、今回は多様性を受け入れるための土台を掘り下げます。
体験を通じて得られる「気づき」は、個人や組織の枠を超え、社会全体に変革をもたらす可能性を秘めています。本記事では、こうした「気づき」がどのように生まれ、多様性の推進に寄与しているのか、3社の取り組みを通じて探ります。
多様な背景の人が働きやすい社会とは?
ーーーバリアフリーや働き方など、現在の日本の「多様性」を受け入れる姿勢にどのような課題を感じていますか?
田中:「都市部とそれ以外とで、かなり大きな差があるように感じています。たとえば、地方の中小企業では、従来の正社員中心の働き方に固執しているケースが多いです。人口減少が進み、人材の母数が減っているにもかかわらず、週5日出勤の正社員を求め続けるのは非現実的です。私たちは外部人材や多様な働き方を活用する方法を提案していますが、情報の開示が足りないために外部人材がうまく機能しないケースもあります。
私たちの会社では、業務委託の方にも経営情報をオープンにすることで、提案力を高め、予想外の成果を生むことができています。このように、地方企業にも情報を開示し、柔軟な働き方を受け入れる姿勢を持つことで、新しい可能性が広がると考えています」
垣内:「日本の都市部ではバリアフリー化が進んでいます。東京の地下鉄ではエレベーターの設置率が97%にも達しており、世界トップクラスです。しかし、地方に目を向けると状況は異なります。バリアフリー化がまだ十分ではなく、交通手段も限られているところもあります。こうした地方の状況を改善するためには、社会全体で意識を共有し、均一化を進めていく必要があると思います」

「多様性を受け入れるためにできることはまだまだある」
と語る株式会社トレジャーフットの田中氏。
「みんなができる」は会社の成長速度を速める
ーーー「多様性を受け入れる」というテーマは重要ですが、実際に企業である以上は利益をださないといけません。生産性の向上と、多様性は経営においてどう関係してると思われますか?
垣内:「多様性を受け入れるというのは、短期的な施策ではなく、長期的な視点で取り組むべき哲学です。組織内で徐々に成熟させ、醸成していくものだと思います。これは時間をかける覚悟が必要ですが、その過程で組織としての芯が強くなり、自然と次のステップに進む力が育まれると感じています。
たとえば、当社では、2010年に全盲の社員を初めて採用しました。最初は、事故やケガが起こらないようにと細心の注意を払いつつも、さまざまな交流の場を作るなどして対応していました。その彼が営業活動を行う中で、門前払いをほとんど受けることなく面談に進めたことは、私たちにとっても新たな気づきでした。現在では、講師として活躍しています。
また、聴覚障害のある社員を採用したことで、会議では音声認識による文字起こしを行うUDトークや字幕付きのツールを導入しました。これにより、会議内容が即座に記録され、リモートや不在の社員にも共有できるようになりました。この取り組みは、当初は障害がある社員のために始めたものですが、結果的に組織全体の効率化に貢献しました。
こうした事例を通じて感じたのは、多様性を取り入れることで、偶発的ながらも組織全体に利益をもたらす成果が得られるということです。同質性だけでは成し得ない発見や成長が、ダイバーシティの実践を通じて得られるのだと思います」

「多様性を取り入れることで、偶発的ながらも
組織全体に利益をもたらす成果が得られる」と垣内。
赤池:「やはり、個々の可能性を信じ、実際に任せてみることが重要だと実感しています。挑戦の中で失敗もあるかもしれませんが、それを通じてお互いが学び合い、信頼関係を築いていく。そうした積み重ねが組織全体の成長を支える基盤になるのではないでしょうか。
私たちの会社では、社員を『仲間』として捉えています。事情のある社員を特別扱いするのではなく、一緒に事業を作り、地域を驚かせていくという姿勢で働いています。このアプローチが、結果として業務フローの改善や、誰もが働きやすい環境作りにつながっていると考えています。
例えば、半身麻痺のある社員が、他の社員から便利な補助具を提案され、それを活用することで業務効率が大幅に向上しました。また、接客のプロセスを誰でも実施できるように設計し直した結果、従業員間のコミュニケーションが活性化し、顧客とのつながりも深まりました。
誰もが働きやすい環境を整えることは、結果的に企業の定着率や収益向上につながると実感しています。ただ、利益を追求するだけでなく、働くことそのものを楽しむ姿勢が、最終的に成果を生むと信じています。事業規模もこの4年間で約5倍に成長しましたが、それは、多様な社員が“もっとやってみよう”と挑戦し続けた結果でしょう」

誰もが働きやすい環境を整えることは、
結果的に企業の定着率や収益向上につながる。
多様性と経済的合理性は両立する
ーーーつまり、多様性を受け入れることと経済的合理性は両立するということでしょうか?
田中:「私たちは『体験を通じた学び』と『ナラティブの共有』を非常に重視しています。社員一人ひとりが現場での経験を通して、多様性に関する新しい視点を得る。そして、それを語り合い、共有することで、組織の文化が変わっていく。そういった取り組みが、今後さらに多様性を受け入れるための鍵になると考えています。
ダイバーシティを取り入れることには、社会性だけでなく経済合理性があると考えています。たとえば、リモート勤務を活用することで、地方在住や介護を必要とする人々がフルタイム勤務を行うのと同等、もしくはそれ以上の成果を上げることができています。このように、多様性を受け入れることは経済的な利益をもたらし、企業にとっても競争力の向上につながります。
重要なのは、障害や状況を理由にして特別視するのではなく、経済性と社会性を両立させる形で、多様性を受け入れる仕組みを作ることです。結果として、企業としても社会としても、持続可能な成長を実現できると信じています」

「語り合い、共有することで組織の文化は変えていける」と会話がはずんだ。
お問合せ
・ミライロ 経営企画部 広報担当
E-Mail:press@mirairo.co.jp