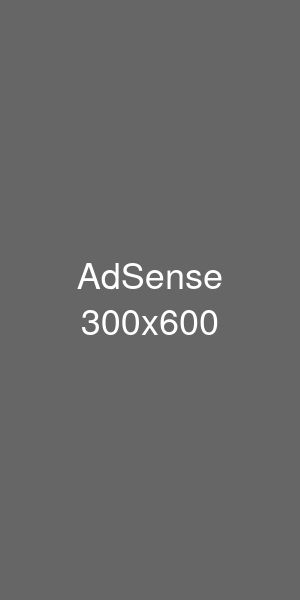改正障害者差別解消法が2024年4月1日に施行されてから1年が経過しました。法改正により、企業には障害のある方々への合理的配慮の提供が義務化され、共生社会の実現に向けた取り組みが求められています。しかし、企業の対応状況を見ると、業界や企業規模によって進捗にばらつきがあるのが現状です。
対応が進んでいる企業では、経営層が積極的に関与し、組織全体での意識改革や具体的なアクションを推進しています。一方で、対応が遅れている企業では、制度の理解不足や実務上の課題が足かせとなり、十分な取り組みが進んでいないケースも見られます。
本記事では、法律の基本的な要件や障害のある方々が直面する配慮不足の課題、企業に求められる具体的なアクションを整理していきます。
目次
・障害者差別解消法について
・不当な差別的取扱いの禁止
・合理的配慮の提供
・合理的配慮の提供における全体像
・法改正の背景
・障害のある方々が日常生活で配慮不足を感じるシーン
・障害のある方々が企業に求める取り組み
・企業の取り組み状況を可視化するミライロの取り組み
・企業の取り組み状況
・過去3年以外に苦情・クレームを受けたことがあるか
・法令遵守から成長戦略へ
障害者差別解消法について

2016年に施行された障害者差別解消法は、共生社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的に制定されました。当初、企業に対する「合理的配慮の提供」は努力義務にとどまっていましたが、2024年4月の改正により義務化されました。
この法律では、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が定められています。まずは、それぞれの概念について解説します。
不当な差別的取扱いの禁止

障害者差別解消法では、障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由とした差別を行なうことを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
たとえば、サービス提供を拒否することや場所や時間を制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることが禁止されています。
合理的配慮の提供

私たちが暮らす社会では、障害のあるさまざまな方が施設やサービスを利用しながら生活しています。しかし、社会の中には、そうした方々の利用を想定していない物やサービスが多く存在し、それがバリアとなっています。
障害のある人が社会に存在するバリアを取り除くために何らかの配慮を求めた際、負担が重すぎない範囲で適切に対応することを求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
たとえば、物理的な環境への配慮として段差を越える際のサポートを行うことや、意思疎通の配慮として筆談やコミュニケーションボードを活用するなどです。また、ルールや運用を柔軟に調整し、手続き方法を変更することも合理的配慮の一例です。
合理的配慮の提供における全体像

上記の図は、障害のある方が合理的配慮を求めるプロセスと対応の方向性を示しています。流れは「環境の整備」→「意思表示」→「合理的配慮の提供」で、対応は個別対応(合理的配慮)と全体的な環境整備に分かれます。
まず、障害のある方が必要な配慮を伝える意思表示が重要ですが、スムーズに行えない場合もあり、声がけや適切なコミュニケーション手段の確保が課題です。企業や施設側は、求められた配慮の可否を検討し、可能な場合は合理的配慮を提供します。負担が大きく即時対応が難しい場合は、「建設的対話」を通じて代替案を検討します。
また、不特定多数が利用する場面では、バリアフリー化や従業員研修などの環境整備をあらかじめ実施しておくことが求められ、長期的な視点での計画が重要です。
法改正の背景

2024年の法改正は、国際的な動向と国内の課題を受けたものです。日本は2014年に障害者権利条約を批准し、障害のある方への差別撤廃と合理的配慮の提供が求められました。しかし、2016年施行の障害者差別解消法では、民間企業の合理的配慮は努力義務にとどまり、対応のばらつきや不十分な配慮が課題となっていました。
障害のある方々からも「必要な配慮が受けられない」「企業によって対応が異なる」といった声が寄せられ、法律の実効性向上が求められていました。こうした背景から、企業の義務化を含む法改正が実施され、社会全体での積極的な対応が必要とされています。今後は、具体的な事例を参考にしながら、適切な対応を進めていくことが重要です。
障害のある方々が日常生活で配慮不足を感じるシーン

当社が行った調査では、障害のある方々が合理的配慮の不足を最も感じるのは「働く場面」「移動の場面」「日常のサービス利用」であり、社会参加や自立した生活に直結する重要な要素であることがわかりました。
特に「仕事や職場」「公共交通機関」「買い物や飲食」で不便を感じる割合が高く、労働環境のバリアフリー化、移動手段の充実、商業施設や公共サービスのアクセシビリティ向上が急務とされています。さらに「医療・福祉サービス」や「災害時」でも十分な配慮が行き届いていない実態が明らかになりました。
こうした課題を踏まえ、社会全体で合理的配慮への理解を深め、具体的な取り組みを強化することが求められます。特に、働く環境や移動手段、日常生活の利便性を改善することが、障害のある方々の社会参画とQOL(生活の質)向上につながると考えられます。
障害のある方々が企業に求める取り組み

障害のある方々が企業に最も求めているのは、経営層の理解と強いコミットメントです。トップが率先して合理的配慮の推進や差別の防止に取り組むことは、単なる環境整備にとどまらず、サービス品質や職場環境の向上にも直結します。経営層の姿勢が明確になることで、従業員の意識が変わり、顧客対応や事業活動全体においてもインクルーシブな視点が浸透していきます。
また、従業員研修や業務改善を通じた社内の意識向上は不可欠であり、組織全体の価値観や企業文化の変革が求められています。合理的配慮を「特別な対応」ではなく、「適切な変更や調整」として根付かせることが、多様な方々が利用しやすいサービスの提供と、誰もが能力を発揮できる職場環境の実現につながります。
重要なのは、環境を整備するだけでなく、それを活かす従業員一人ひとりの意識と企業全体の姿勢です。
企業の取り組み状況を可視化するミライロの取り組み
障害者差別解消法の改正を受けて、多くの企業が「何から取り組めばよいかわからない」「現状の対応が十分かわからない」という課題を抱えていました。そこで、当社では「ミライロ・サーベイ(※)」を開発し、企業の障害者対応を客観的に評価、改善策を提案する仕組みを構築しました。現在、約200社の企業がミライロ・サーベイを活用しています。
このサーベイでは、企業の取り組みを以下の5つの観点から分析し、課題を明確にしています。本記事では、サービス面のミライロ・サーベイの結果をご紹介します。
1.経営層のコミットメント
2.従業員研修やオペレーション
3.多様な顧客対応や相談窓口の設置
4.施設のバリアフリー化
5.情報アクセシビリティ
今回は、従業員500名以上の企業のデータをもとに、企業の取り組み状況を詳しく分析します。
企業の取り組み状況

ミライロ・サーベイ(サービス版)を実施した企業の特徴として、従業員数は1,000人以上5,000人未満の企業が最多であり、売上規模では500億円以上1,000億円未満の企業が最も多いです。特に、顧客対応が求められる業界(サービス業・金融業)が多く含まれ、障害者対応への関心が高いことが特徴です。
業界別の取り組み状況

上記は、ミライロ・サーベイの約50問の設問に対して「当てはまる(4点)/やや当てはまる(3点)/あまり当てはまらない(2点)/当てはまらない(1点)」の4段階で評価いただいた情報をスコア化した表です。
全体的な傾向
経営層のコミットメントが高い業界や企業ほど、他の取り組みも進んでいる傾向が見られます。5つのカテゴリーの平均スコアは1.9(4点満点)と全体的に低めの評価となりました。特に評価が高かったのは「経営層のコミットメント」(2.4)、次いで「従業員研修・運用オペレーション」(2.0)。一方で、「施設のバリアフリー化」(1.6)と「情報アクセシビリティ」(1.5)の評価は低く、業界を問わず改善の余地が大きいことが分かります。
経営層のコミットメントが高い業界と低い業界の比較
高評価 金融業界(平均スコア:2.3)
・「経営層のコミットメント」(3.0)、「従業員研修」(2.4)のスコアが高く、組織的な取り組みが進んでいる。
・業界全体で障害者対応を強化する意識が根付いている傾向がある。
低評価 サービス業(平均スコア:1.7)
・全カテゴリーで最低評価を記録。
・特に「施設のバリアフリー化」(1.4)、「情報アクセシビリティ」(1.3)の遅れが顕著。
上記のことから、業界によって企業の障害者対応の進捗に大きな差があることが分かります。金融・小売業界は比較的先行している一方で、サービス業は遅れが目立ち、重点的な改善が必要です。
また、「情報アクセシビリティ」と「施設のバリアフリー化」はどの業界でも低評価となっており、業界全体として取り組むべき共通課題といえます。しかし、施設のバリアフリー化などのハード面の改善には、まとまったコストや時間を要するため、短期間での対応が難しい企業も少なくありません。そのため、まずは経営層のコミットメントを起点に、社内の意識醸成や企業風土の形成を進めることが重要です。経営層が障害者対応を企業の成長戦略の一環として捉え、従業員一人ひとりの意識改革を促すことで、現場レベルの取り組みが加速し、持続可能な改善につながるでしょう。
過去3年以外に苦情・クレームを受けたことがあるか

加えて、約4割の企業が過去3年以内に障害のある方へのサービス提供に関する苦情・クレームを経験していることがわかりました。障害者対応の充実は企業にとって避けて通れない課題となっています。対応の遅れは、顧客満足度の低下や企業のブランド価値の毀損にもつながりかねません。
企業は今後、法令順守はもちろんのこと、積極的に施策を講じる必要があります。まずは経営層が率先して方針を示し、社内全体で意識を高めることが、持続可能な取り組みの第一歩となるでしょう。
法令遵守から成長戦略へ

障害のある方々への配慮を進めることは、高齢者や子ども、外国人、妊娠中の方、けがをしている方など、多様な背景や状況にあるすべての人々の利便性向上にも寄与します。例えば、段差をなくした施設設計や、誰にでもわかりやすい案内サインの導入は、障害のある方のみならず、あらゆる人にとって利便性を高める取り組みとなります。
こうした施策は、企業が社会的責任を果たしているという信頼につながり、顧客や利用者から選ばれる要因となるだけでなく、組織のブランド価値向上や新たなファン層の獲得、さらには従業員満足度の向上にも結びつきます。結果として、企業の持続的な成長を支える重要な要素となるのです。
積極的に取り組みを進める企業の中には、単なる法令順守を超え、障害者対応を競争優位性の一つとして捉え、企業価値の向上や新たな市場機会の創出につなげている企業も増えつつあります。この動きは、社会的責任の観点だけでなく、企業の持続的な成長戦略としても極めて重要な要素です。
当社としても、こうした取り組みをさらに広げ、共生社会の実現に向けて、企業や関係者の皆さまとともに歩んでいきたいと考えています。本記事が、改正法施行後の現状を振り返り、より良い取り組みを共に模索するきっかけとなれば幸いです。

ミライロは企業ごとの課題やニーズに合わせて総合的なサポートを行なっています。合理的配慮や環境整備など具体的なサポートをご希望の場合はご相談ください。
▶お問い合わせはこちら
ミライロ・サーベイについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
▶ミライロ・サーベイはこちら
企業が取り組む事例を知りたい方は、こちらをご覧ください。
▶導入事例はこちら