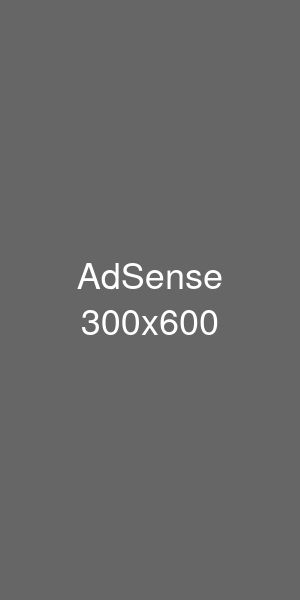普段何気なく使っている「障害」という言葉。みなさんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。
一体どんな意味があるのでしょうか。
一緒に考えてみましょう。
障害者の「障害」とは
「障害」という言葉の意味を調べてみると、「ものごとの達成や進行のさまたげとなること、もの」と書かれています。
障害は無いほうが良いもの、取り除いたほうが良いもの、と考えられることが多くあります。
「障害者」についてはどうでしょう。
よく、「かわいそう」「大変そう」と言われることがあります。
なぜそのように感じるのでしょうか。
障害者が「大変そう」だと感じる時はどんな時か。
例えば、
車いすユーザーが階段を目の前にした時。
目の見えない方が書かれている文字を読みたいと思った時。
聴覚障害のある方が音声情報を聞きたいと思った時。
その方々にとって「障害」を感じる瞬間でもあります。
しかし、これは障害者本人が「障害を持っている」というわけではありません。
周りの環境が「障害になっている状態」なのです。
つまり、障害とは「人ではなく、環境の側にある」ということなのです。

なぜ障害と感じるのか
街にある施設や設備は、大多数の人に合わせてつくられています。
このような環境の中で車いすユーザーが感じる障害は、超えられない段差や階段があることです。
残念ながら街中には当たり前のように段差や階段があります。
その理由は、大多数の人は歩けるからです。
歩ける人にとって便利に作られているわけですから、歩けない人にとっては障害を感じる場面がたくさんあるというわけです。
また、段差や階段を同じように障害と感じている人は、車いすユーザーだけではありません。
ご高齢の方、ベビーカーを押している方、荷物を沢山持っている買い物帰りの方、怪我をしてる方などいろんな方がいます。
もしこの障害を解消することができれば、障害者だけでなく、多くの方にとって過ごしやすい環境につながるかもしれません。

そうやって周りを見渡すと、景色が少し違って見えてきませんか?
いろんな場所や場面において、
障害を感じ困っている人はいないかな。
どうやったら解消できるかな。
そのような視点で見ることができるのではないでしょうか。