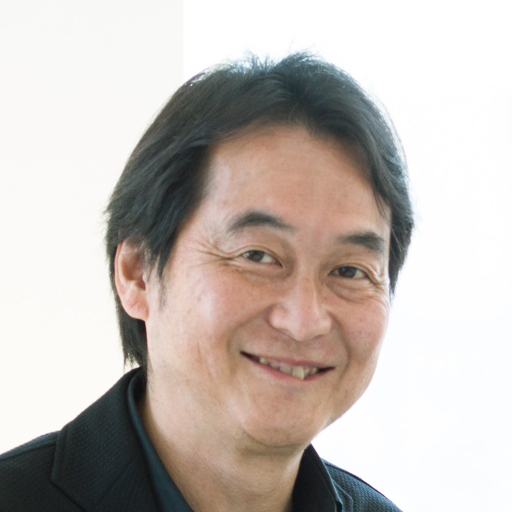

































































NTTドコモで「iモード」「おサイフケータイ」など、当時革新的なモバイルサービスを次々と立ち上げた、夏野剛さん。日本の経済と課題を冷静に見つめ、新しい時代を牽引するビジネスリーダーとして、世界から注目されています。夏野さんに、2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機として、日本の起こるテクノロジーと意識の進化が持つ可能性について、伺いました。
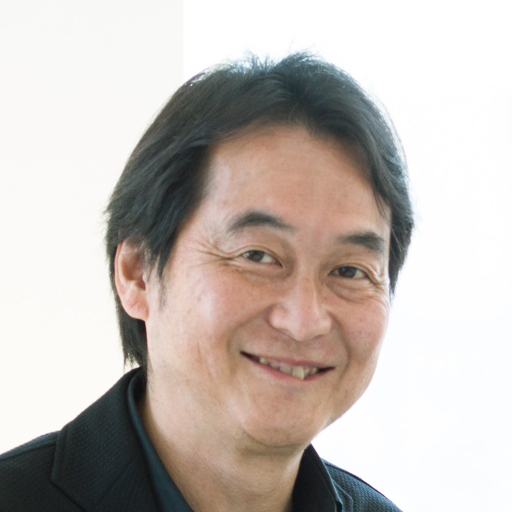
1988年早稲田大学政経学部卒業、東京ガス入社。95年ペンシルバニア大学経営大学院卒業。ベンチャー企業副社長を経て、NTTドコモへ入社し、執行役員を務め2008年に退社。現在はドワンゴ、セガサミーホールディングス、ぴあなど複数の取締役を兼任、慶應義塾大学環境情報学部では客員教授を務める。
自らが語る弱み(バリア)は「音楽が好きなのに楽器が演奏できないこと」。逆手に取って語る強み(バリュー)は「世界一流の音楽を聴くために、深く集中できること」。

1989年に愛知県安城市で生まれ、岐阜県中津川市で育つ。生まれつき骨が脆く折れやすいため、車いすで生活を送る。自身の経験に基づくビジネスプランを考案し、国内で13の賞を獲得。障害を価値に変える「バリアバリュー」を提唱し、大学在学中に株式会社ミライロを設立した。高齢者や障害者など誰もが快適なユニバーサルデザインの事業を開始、障害のある当事者視点を取り入れた設計監修・製品開発・教育研修を提供する。

夏野さんとは、よくお仕事の相談をさせていただいていますが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員でご一緒したのが、印象深いです。
そうですね。垣内さんを始め、委員会には色んな障害のある人がいたのが、本当に良かったと思います。議論をする度に、新しい気づきがありました。


そう言ってもらえて、嬉しいです。
マスコットの選定方法を決める議論は特に、多様性が存分に発揮されていたと思います。


東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の(以下、オリパラ)マスコットキャラクターは、最終候補デザイン3案の仲から、全国の小学校1万6769校のクラス投票により決定されました。
普通小学校だけじゃなくて、障害のある特別支援学校の子どもたちにも投票してもらうべきだ、とかですね。


当たり前のようですが、当事者がいないと見落としてしまうかもしれないアイデアですね。
組織委員会だけではなく、企業組織においても言えることですが、同じバックグラウンドの人ばかりで議論しても良い結果は残らないんです。


どうしてですか?
同じバックグラウンドの人が言うことは、だいたい想像も理解もできるからです。僕は、人間が一番成長する瞬間って「自分が気づかなかったことに、気づいて、視野が広がった時」だと思うんです。


なるほど。
色んな視点を交えて、一つのことを真剣に議論すると、良い結果が残りやすいです。


でも、そうすると、摩擦も起きますよね。
良いじゃないですか。摩擦が起きて、反対意見が生まれるから、自分の意見を検証したり、説得するために知恵を絞ったりするんです。それで自分の考えを深めるのが、成長です。


企業の経営では、どうしても似通った同質の人を集めがちなので、意識しなければいけないですね。
異質の人を歓迎し、組織内で摩擦を起こし、高め合うのが、今や世界のスタンダードです。日本はまだ遅れを取っているので、世界会議を見ても、議論が下手な経営者が多いなという印象です。


異質を好意的に受け入れ、摩擦をちゃんと受け止められる人が、日本ではまだ少ないんですね。

オリパラをきっかけに、日本中でイノベーションは起こるのでしょうか?
領域によります。オリパラは「人」が活躍するイベントだから、テクノロジー領域のイノベーションは起きづらいと思います。しかし、意識のイノベーションは間違いなく起きます。


意識のイノベーションですか?
例えば、オリパラをきっかけに、2017年からJPN TAXI(ジャパンタクシー)が導入されましたよね。

JPN TAXIとは、2020年オリパラを契機に生まれた新型タクシーです。「おもてなしの心」をテーマに開発され、開けやすいスライド式ドア、車いす利用者向けの折りたたみ式スロープ、海外環境客を意識した広い荷物スペースなどが特徴です。

JPN TAXIに搭載されている機能はすべて、2017年よりずっと前に完成していたのに、広がらなかったんです。


オリパラを契機に、必要性が増して一気に広がりましたね。
耐震対策なんかも、同じですよね。大きな災害が起きて、ようやく皆が、多少高価で手間がかかったとしても、耐震のテクノロジーを導入してみようと思うわけです。


駅のバリアフリー化も、です。東京の駅のバリアフリー化率は68%でしたが、今は88%まで一気に改善されました。
意識のイノベーションの効果です。みんなの意識が「そうだ!必要だ!」に変わった瞬間、テクノロジーが生きてきます。


テクノロジーの進化は、人の意識の変化と、一緒に起きてこそ意味があるんですね。
それを僕は、テクノロジーの社会適合と呼んでいます。日本はとにかく、社会適合が遅かった。

1996年、Yahoo!Japanの登場とともに起きた日本の「IT革命」。パソコンは1人1台が当然になり、スマートフォンによりいつでも手の平から世界につながることができる時代になったのに、日本はその波に乗り遅れた、と夏野さんは言います。
1996年から2016年までの20年間、日本のGDP成長率はたったの2%。一方、アメリカのGDP成長率は129%。夏野さんはその理由を、新しいITという文化をさまざまな産業に取り入れたアメリカと、二の足を踏んでいた日本との違いだ、と説明しました。

テクノロジーがあっても、人の意識や社会のシステムに沿わなければ、ダメなんです。出遅れた分、一刻も早くムーブメントを起こして、遅れを取り戻したいですね。


オリパラが、テクノロジーの社会適合の機会になるんですね。楽しみです!
ラグビーワールドカップの盛り上がりで確信しました。開催をきっかけに、クレジットカードや電子マネーのキャッシュレス決済が使えるお店が一気に増えて便利になりましたから。


外国の方々からは、とても好評だったそうですね。
キャッシュレス決済が浸透して、税金の還付まで受けられるようになったんですよ。素晴らしい!


ラグビーワールドカップやオリパラの開催が決まって、それらに向けて急いで整備を進めてムーブメントが起きたら、訪日外国人も増えて、良い循環になりましたよね。
2012年から2017年までで、訪日外国人数は3.5倍、消費額は4.4兆円という凄まじい経済効果がありました。


これから大阪万博も開催されると、ムーブメントはより加速しますね。
イベントをうまく使いながら、テクノロジーの社会適合を起こして、日本を進化させていくのが理想です。


外国人だけではなく、障害のある人やご高齢の人にとっても、便利で外出しやすい日本になりそうです。

日本を進化させることに関連して、お聞きします。夏野さんは、ご著書で「日常の不平不満は表裏一体」と言われていますよね。
はい。そのとおりです。


夏野さんが、不平不満を感じたことで、チャンスが生まれた事例はありますか?
いっぱいあります。例えば、「おサイフケータイ」も、僕が持っていた不平不満がきっかけでした。僕は昔から、小銭が大嫌いだったんです。


小銭が大嫌い!?
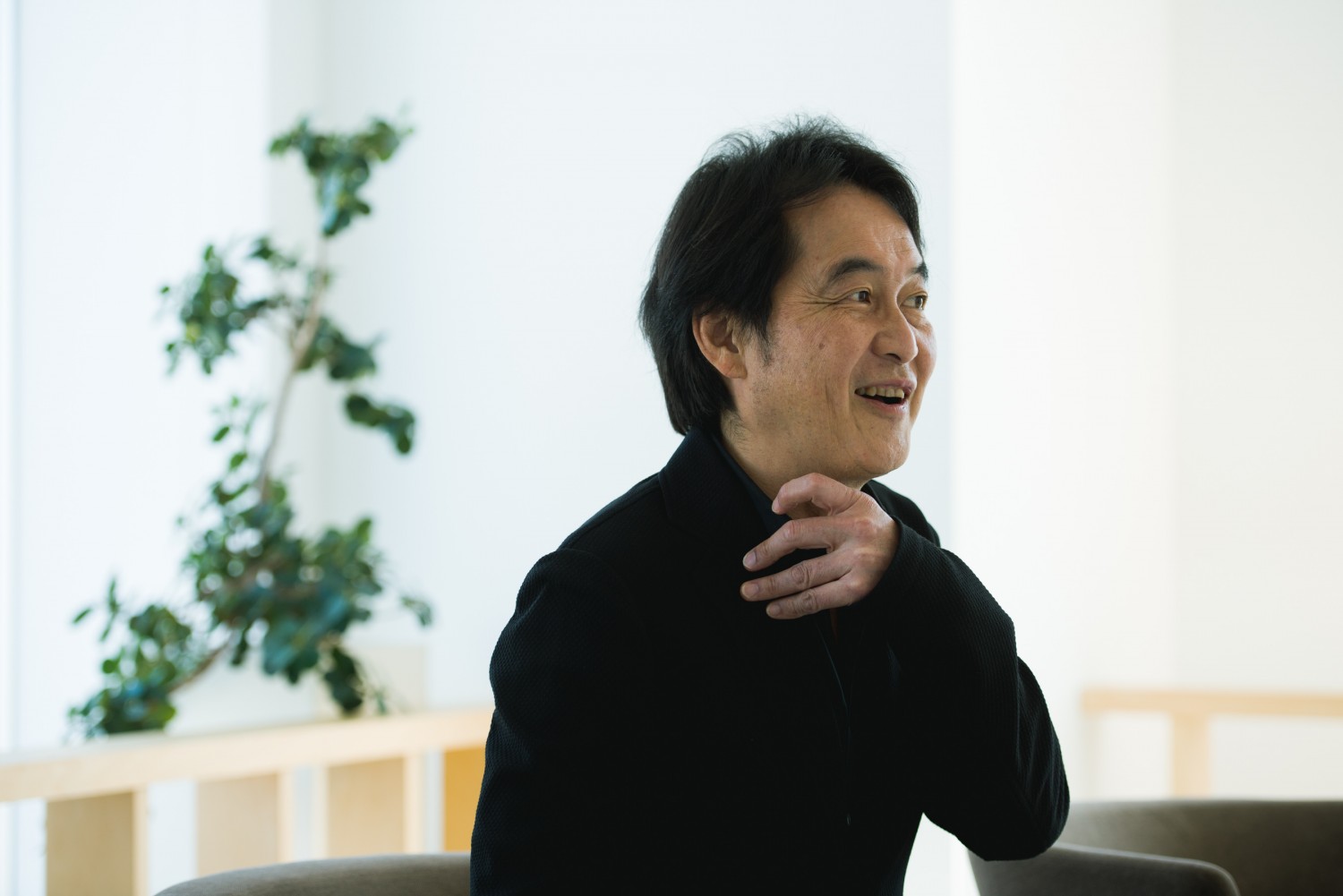
まず親から「小銭は不潔だから、触ったら手を洗いなさい」と言われて育ったんです。なんでそんな汚いものが流通しているのか、子どもの頃から不思議で仕方ありませんでした。


なるほど……。
しかも、ジャラジャラして、かさばるし。僕が育った金沢の田舎街は、主な移動手段がバスだったんですけど。毎日毎日、乗車料金の支払いや両替に、すっごい時間がかかってたんですよ。邪魔くさくて仕方なかったです。


子どもの頃から持っていた不平不満が、「おサイフケータイ」の開発に繋がったんですね。
そうです。いつも持ち歩く携帯電話にお財布の機能があれば、ストレスもなくなるだろうと思って。


「おサイフケータイ」の登場は2004年ですよね。キャッシュレス決済がブームになる15年以上前から、世界に先駆けて発表されたのは、凄まじい先見の明だと思います。
「iモード」も、PCを持ち歩かないとインターネットに繋げられないという不便な思いから生まれました。不平不満をやみくもにぶつけるのではなく、解決するにはどうしたら良いかを考えるから、イノベーションが起きます。


不平不満を、前向きに捉えているんですね。
不平不満には二種類あります。大切なのは、社会の制度や企業の製品への不平不満。これは僕だけが怒っているのではなく、消費者みんなが困っていること。つまり“義憤”です。


義憤ではない不平不満は?
妬みとか、愚痴とか、発信してもどうにもならない怒りですね。義憤は社会を進化させるきっかけになるので、積極的に発信したり、解決しようと一歩を踏み出したりすべきだと思っています。


義憤を発信すると、反対意見なども多く集まりますか?
はい。学びになる意見は受け入れますが、そうではない意見は、何を言われてもまったく気にしません。スルーしています。


なるほど。気にしない、という勇気も大切なんですね。
どんな意見にも必ず、反対意見があるんです。「iモード」を発表した時は、革命だと賞賛され、世界中のビジネス誌の表紙を飾りました。それでも、色んなことを言われ、邪魔をされたこともありました。



そこまでの成果をあげてもなお、反対意見があったんですか。
はい。でも、開き直って「ここまでやりきっても何か言われるなら、学びになる意見以外は気にしないでおこう」と思えるようになりました。


前向きな開き直り、ですね。義憤で行動することに、誰しも少なからず怖さを持つと思うので、勇気が出る心構えだと思います。
バリアフリーの領域なんて、まさに義憤だらけですよね。


はい。車いすに乗っている私の「不便だな」「嫌だな」という義憤から生まれたサービスも、数多くあります。
最初は自分が起点でも、それは皆が求めているソリューションなんです。自分の力で義憤を解決していくプロセスが、僕はとても楽しいと思うんです。



