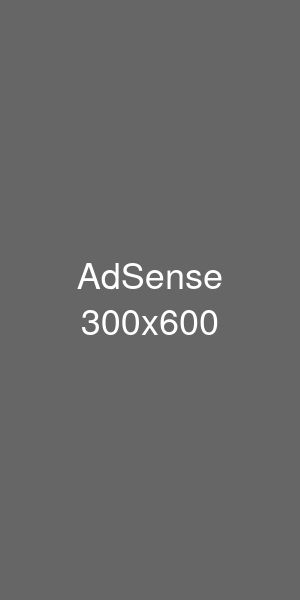みなさんは
「車いすで通行できる幅はどれくらいだろう?」
「無理なく上がれる段差の高さはどれくらいだろう?」
などと思われたことはないでしょうか。
今回は設計時や普段の生活の中で知っておくと役立つ10の数値をご紹介します。
2cm
「2cmの高さ」と聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。
車いすユーザーやベビーカーユーザー、ご高齢の方などにとって、ほんのわずかな段差でもバリアとなる可能性があります。
そのため、床面はできるだけフラットであることが望ましいですが、バリアフリー法では横断歩道と歩道の間の段差の基準を2cmとしています。
これは、視覚障害の方が車道と歩道の境目を認識するためです。
最近では、車いすユーザーが通行する部分の段差だけ、切り下げている歩道があります(写真2枚目)。
車いすやベビーカーをご使用の方と視覚障害の方、両者の利便性を保つ工夫です。


30cm
点字ブロックには、進行方向を示す「誘導ブロック」と危険箇所などを示す「警告ブロック」の2種類があります。
これらの設置位置として、点字ブロックと障害物を離す目安は約30cmとされています。
例えば、階段の前後に設置される警告ブロックは、階段から約30cmの距離を置いて設置されます。
この距離を保つことで、視覚障害の方が事前に障害物があることを認識することができます。
また、誘導ブロックは周囲30cm以内に障害物がない場所に設置することが求められます。
街中を歩いていると、点字ブロックの上に物が置かれていたり、点字ブロックに非常に近接する距離に障害物があったりすることがあります。
点字ブロックの近くに障害物が無いか、身近な場所で是非ご確認いただければと思います。

職場内のユニバーサルデザインをチェックしたい方は、こちらのユニバーサルデザインチェックリストを是非ご活用ください♪ |
45cm
車いすの座面の高さは約45cm、これは一般的な椅子より少し高い設定です。
車いすから他の場所へ移乗する際には、この座面の高さと同じ程度の高さの場所が移乗しやすいとされています。
この高さを見落としがちな例として、広々としたバリアフリールームを設けているのにもかかわらず、そのベッドの高さが高いばかりに、障害当事者が快適に過ごせないといったケースがあります。
特に長い時間を過ごす場所では、車いすでの移動だけではなく、車いすからの移乗についても想定しておくことが求められます。

70cm
JIS規格で定められている一般的な車いすの幅は70cm以下とされています。
海外製の車いすの中には、もう少し広い幅のものもあります。
この車いすの幅を1つの基準として、空間づくりにおける様々な寸法が導き出されます。
80cm
車いすで通過できる出入口の幅は80cm以上とされています。
JIS規格の車いす幅が70cm以下と考えると、手や腕をぶつけずに通るためには80cm必要であるということが見えてきます。
また、車いすを使用する方だけでなく、杖を使用する方にとっても十分な幅が必要です。
この寸法は計画上の寸法ではなく、有効寸法であることが求められます。
扉の引き残しの関係などにより、完成した際に80cmを満たさないケースも見受けられますので、計画時や扉の選定時には、注意したい部分です。
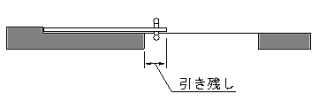
90cm
さらに、車いすで通行しやすい通路幅は90cm以上とされています。
出入口は通過できる寸法ですが、通行するとなると走行するための余裕が必要となるためです。
110cm
車いすユーザーの目線高さは約110cmです。
そのため、サイン計画においては立っている人が視認できるだけでなく、車いすユーザーや子どもからも見やすいものかを検証することが求められます。
また、この寸法は照明スイッチやエレベーターのボタン等の高さとしても推奨されるもので、立っている人も座っている人もアプローチできる高さとされています。
120cm
先ほど車いすユーザーが通行しやすい幅としては90cm以上と記載しましたが、人とすれ違うためにはその分の幅が必要となります。
車いすユーザーと人が通行できる幅としては120cm以上が目安となります。
ユニバーサルデザインやバリアフリーにご興味のある方は、情報を伝えやすくするヒントがわかる資料、バリアフリーマップ~4つの作成ポイント~もチェックしてみてください! |
150cm
さらに、通行するだけでなく車いすで回転するためには十分な幅が必要となります。
車いすで回転するためには150cm以上の幅が目安となります。
エレベーター前や多目的トイレ内、スロープの前後などに車いすで回転できるスペースがあるかは確認が必要です。

350cm
優先駐車場の幅としては350cm以上が求められます。
一般的な駐車場の幅は250cmですから、+100cmの幅が必要となります。
これは、先に記載した車いすで通行できる寸法や車の扉の開閉の幅を考慮すると、必要になることがイメージしていただけると思います。
まとめ
以上、ユニバーサルデザインで知っておくと役立つ10の数値をご紹介しました。
いずれも人間工学や車いすの寸法に基づいて導き出された数字ですが、あくまでも基準としての寸法であり、身長や手の届く範囲、車いすの大きさ等は人それぞれです。
ミライロでは障害当事者の実際の利用を想定した空間づくりのお手伝いをしています。
後から改修を加えることは多大なコストがかかりますが、最初からバリアをつくらなければ管理コストを削減することができます。是非参考にしてみてください。
バリアを作らないための参考資料、ユニバーサルデザインチェックリストはこちらからダウンロードいただけます。