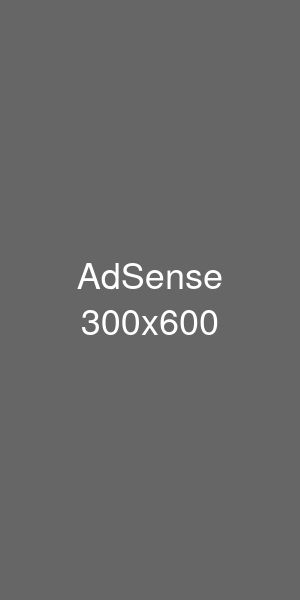我が国において、商業施設や公共施設他の不特定多数の方々が利用する施設のユニバーサルデザインはかなり整備が進みました。
それと比較してオフィスのユニバーサルデザインの現状は、最も遅れている分野です。
オフィスのユニバーサルデザイン
オフィスのユニバーサルデザイン(以下、UD)において重要なことは、物理的な数値の問題ではなく多様な人々をいかに受け入れる空間であるか、ということだと考えられます。
障害者、外国人、LGBTの方々、全員が100%の満足度に達成することは、困難です。
したがって、ミニマムでシンプルなデザインを基本にして、特別なニーズを求める人とは、その都度話し合いをすれば良いことです。
すなわち、選択の余地があることが重要です。
では、具体的に基本的な考え方をあげていきましょう。
①安全に避難できること
何は無くとも非常時の避難が最も重要です。
警報は視覚聴覚両方に訴えるものとします。
車いすユーザーの避難経路や避難用具を準備してください。
また、すばやく移動できない人への人的サポートとその訓練も必要となります。

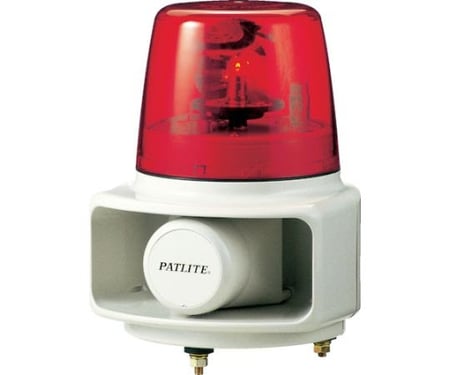
②安全に移動できること
車いすユーザーと歩行者とのすれ違いできる通路幅は120cm、交差点や方向を変えるスペースは150cm円が必要です。
セキュリティゲート幅も80cm以上あるか確認が必要です。
床面は出来るだけフラットとし、段差や斜面がある場合は、床の色にコントラストを付けたり、素材を変えたりするとよいでしょう。
大きなガラス面には衝突防止用のシールを張り、誤って衝突することを防ぎます。
何より重要なのは、その通路に段ボールや鞄、ごみなどの通行を妨げるものを置かないことが大切です。
③だれでも知ることができること(サインの設置)
多数の言語で記載するのは限界があるので、ピクトグラムや色分けを利用して言語に頼らない、誘導や危険表示、使用法を掲示します。
オフィスのユニバーサルデザイン環境を簡単にチェックできるユニバーサルデザインチェックリストも併せてご確認ください。 |
④フレキシブルなワークスペース
椅子は肘掛けのあるもの(起立補助や休憩姿勢、片腕の重量4kgの加重負担に必要)が望ましいです。
デスクの理想は座位から立位まで対応できるもの。
机の高さは、体格に合わせ椅子の高さを決めてから机の高さを調整するのがよいです。
足のむくみ、肩こりの防止に有効です。
キャビネット内の使用頻度の高い書類は、車いすユーザーが出し入れしやすいようにキャビネット内の床からに二段目を空けておくなど本人が使えるようにする配慮も必要です。
⑤ホッとする休憩室の設置
休むだけではなく、社員同士のコミュニケーション活性の場でもあります。
コミュニケーションの活性化はUDで最も必要なことです。
より活発なコミュニケーションを促すために執務室からの視線や音をシャットアウトする工夫が必要です。
⑥トイレ
内部で車いすが回転できる150cm円が確保できるものが理想ですが、それが必須では無く使用者との話し合いで解決する場合もあります。
チェンジングボードは男女問わずあると良いです。
ダイバーシティ&インクルージョン
さて、オフィス環境は整いましたが、ここが大切です。
自分のオフィスのとなりの席に、今まで接した経験のない、いろいろな人がやってきて一緒に仕事をするんです。
日本人は、多様性が大事だと口では言いながら、違和感を覚えている方々が大半だと思います。
それは、日本の国会を見てみればわかります。(日本の女性国会議員比率(衆院)は10.1%で、193カ国中157位だった。列国議会同盟2018)
女性でさえその状態です。
海外では色々な人がいて当たり前、普通のこととなっています。
企業の成長のためには国籍、性別、障害、身分、宗教などは問わず、良い人材を招き入れるためにユニバーサルデザインが必要と考え、それが企業理念と一致したのです。
したがって、オフィスのユニバーサルデザインは、CSRでも、福祉でも、義務でも無く、経営戦略であります。
しかしながら、やっぱり荷が重いと感じてしまう日本人は多いのではないでしょうか?
日本人のほとんどは、となりの人も日本人、障害者とも外国人ともLGBTの人とも共に生活をしたことが無いし、関心も無かったからです。

となりの〇〇さんと話す
どんなに、施設環境を整えたとしても、オフィスで働くのは人です。
ユニバーサルデザインが成功するか否かは、そこで働く人次第なので、企業の経営の問題となってきます。
ただ多様な人材を受け入れて働きやすいオフィスを作るだけのことではありません。
企業の考え方や視点を多様化させ、さまざまな顧客ニーズに応えたり、柔軟なアイディアや革新的な製品を生み出す為に不可欠な考え方です。
トップ自らがユニバーサルデザインを推進することを表明し、社内外に理解を求めること。
少数意見が軽視されないコミュニケーションの仕組みつくりが必要となります。
さあ、となりの人と話を始めましょう。
まとめ
となりの〇〇さんと生活したことが無くても、学ぶことはできます。
気軽に向き合うことができ、コミュニケーションを重ねることでユニバーサルデザインを推進して行くことが可能となります。
障害のある職員とのコミュニケーションや向き合い方を学んでみたい方には、こちらの検定がおススメです。ユニバーサルマナー検定のご案内
また、オフィスのユニバーサルデザインについて簡単に見直せる便利なチェックリストはこちらのリンクからダウンロードください。
障害者雇用を推進する職場づくりのためのユニバーサルデザインチェックリスト