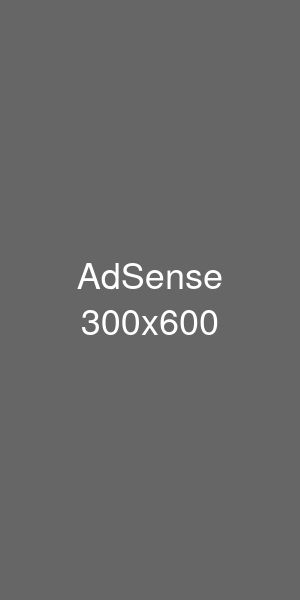弊社は、障害を価値へと変える「バリアバリュー」の企業理念のもと、「環境」「意識」「情報」のバリア解消に取り組んでいます。
その中でも、情報のバリア解消にフォーカスを当て、弊社が運営するプロダクトを数回に分けて紹介していきます。
今回は、2019年7月にリリースした、障害者手帳アプリ「ミライロID」の開発のきっかけをお伝えします。

スムーズに外出するために
バリアフリー地図アプリ「Bmaps」のリリースから3年。
皆様のおかげで、20万件以上のバリアフリー情報が登録されました。
Bmapsで調べれば、障害のある方々が入店できる施設は、ある程度の数がわかるようになりました。(20万件以上/2020年5月1日現在)

▲ 六本木周辺のバリアフリーな施設
※「Bmaps」に関する詳細は、こちら
そのような中、ユーザーから
「Bmapsによってバリアフリーな施設はわかるようになったが、外出時の不便は解消されていない」
といったお声をいただきました。
よくよく話を伺ってみると、その要因の一つが障害者手帳にあることがわかりました。
障害者手帳の問題点
障害者手帳は障害があると証明したり、各種割引を受けたりするのに必要ですが、持ち歩くことに不便さがあるとのことでした。
実際、弊社の垣内も、その不便さに長年向き合ってきました。
■障害者手帳
障害がある人に都道府県知事らが交付する手帳。
大きさなど様式は自治体により異なる。
手帳があると、税金の減免や公共料金の割引などが受けられる。
民間企業のサービスは事 業者の判断で行われ、割引の内容はさまざま。
そこで、「ミライロ・リサーチ」の障害者モニター約400人に調査を行ったところ、約7割が「取り出すのが手間である」と回答しました。
ページをめくらないと必要な情報が出てこない点、持ち歩くことで劣化する点などに「不便だ」の声がありました。
また、紛失のリスクもあります。
※「ミライロ・リサーチ」に関する詳細は、こちら
※「障害者手帳の利用状況に関する調査結果」は、こちら
事業者にとっても負担
調査を進めていく中で、障害者割引の適用時に手帳を確認する事業者も、課題を感じていることがわかりました。
障害者手帳の発行は自治体に委ねられているため、フォーマットが多岐にわたっています。
その数にして、約300種類。
自治体毎に規格が異なっており、必要な情報を瞬時に判別できない、確認をする際に時間がかかるといった問題を抱えていました。

障害者手帳をあなたのスマホへ

外出する障害者、向き合う事業者、双方の課題を解決するため、ミライロIDは生まれました。
使い方は至って簡単で、障害者手帳の必要なページを写真に撮って電子化し、あとはミライロIDが使える施設や窓口で、スマホ画面を提示するだけです。
障害者は、持ち歩く手間や、取り出す負担を軽減できます。
スマホはロックがかけられ、セキュリティー面でも安心感があります。
車いすの仕様や大きさなどの情報を追加することもできます。
事業者にとっては、約300種類の障害者手帳が1つのフォーマットにまとまるため、確認すべき情報をひと目で把握できるといった利点があります。
人と企業をつなぐ障害者手帳アプリ、それがミライロIDなのです。
使える場所の拡大に向けて
前述の通り、障害者割引の適用方法は、各事業者に任されています。
2019月には、国土交通省が公共交通機関の事業者に対し、割引の利用者に過度な負担とならない方法にするよう求めました。
このような動きも受け、現在、約500の事業者がミライロIDを本人確認手段の一つとして認めています。
※「使える場所」は、こちら
ミライロIDの使える場所が増えば増えるほど、利便性は高まります。
皆さんと一緒に、障害のある方が外出しやすく、事業者の対応もスムーズになる、新たな未来を実現させたいと願っています。
障害者割引を設けている事業者は、ミライロIDの導入にぜひご協力ください。
※導入をご検討の事業者は、こちら

ミライロIDは、こちらからダウンロードすることができます。