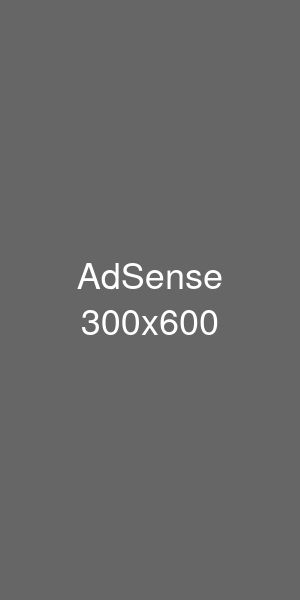前回の記事では、インクルーシブな演劇空間を実現するための6つのポイントのうち、ポイント①~③をご紹介しました。
※インクルーシブな演劇空間を実現する6つのポイント【前編】
今回は引き続き、国土交通省が策定した「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 (平成28年度版)」をもとに、ポイント④~⑥をご紹介します。
ポイント④経済性・柔軟性・効率性に配慮する
障害者や高齢者だけに対応するのではなく、他の利用者も同じように利用できる空間づくりを目指しましょう。
設備の機能を状況に合わせて変化できるようにすることで、効率よく活用できるように計画します。
【具体的な例】
- 客席に可動席スペースを設けることで、 多様な利用者に対応する。
- 視覚障害者や聴覚障害者の鑑賞をサポートする小型受信機を使用し、外国人への情報保障も行う。
- トイレでは、車いすユーザーやオストメイト、乳幼児連れ利用者などに対応した個別機能を備えたトイレと、多機能トイレの設置によって機能を分散させる。
- 男女別のトイレ数が利用者の数に合わせて、変更が行えるように計画する。

限られた空間を効率よく活用し、利用の幅に柔軟性を持たせることによってコスト削減にもつながります。
ポイント⑤施設内における情報提供を行い、わかりやすさに配慮する
劇場内の全体構成や、設備の機能、動線の情報を案内表示(案内板、表示板など)に取り入れることで、障害者や高齢者を含むすべての利用者にとってのアクセシビリティが向上します。
【具体的な例】
- 空間に溶け込まないように、案内表示を目立つ位置・高さに設置する。
- 案内表示は、適切な照明の明るさのもとに設置する。
- 案内板前に点字ブロックを設置する。音声案内を取り入れることで、注意をうながす。
- 案内板の表示に、ピクトグラムや多言語表記を取り入れる。
- 色にコントラストをつけ、適切な文字・ピクトグラムの大きさで表示する。
- 点字や浮き出たサインによって触れて情報を得られるようにする。
案内表示は、様々な利用者の動線を想定して設計する必要があります。
より分かりやすい情報提供を行うためには、障害のある当事者を含めた利用者の視点で考えていく必要があります。
ポイント⑥利用者の特性・ニーズに合わせたスタッフ配置を計画する
施設管理者や公演の主催者は、障害者や高齢者など多様な利用者の案内・誘導に必要なスタッフの配置、サポート方法を計画しましょう。
【具体的な例】
- 利用者の特性とニーズを把握し、自分とは違う誰かの視点に立ち行動することを心がける。
- ユニバーサルデザインに対する理解を深めることで、サービス向上を目指す。
- サポートを必要とする方に対して、「何かお手伝いできることはありますか?」と声をかける。

設備面のハードはすぐに変えられなくても、私たち一人一人のハートは今すぐに変えることができます。正しいサポート方法を身につけ、利用者が安心して利用できる空間づくりを目指しましょう。
まとめ
【インクルーシブな演劇空間を実現する6つのポイント】
①誰もが同じように利用できる動線を計画する
②適切な寸法を計画する
③多様なニーズに合わせた客席の種類を提供する
④経済性・柔軟性・効率性に配慮する
⑤施設内における情報提供を行い、わかりやすさに配慮する
⑥利用者の特性・ニーズに合わせたスタッフ配置を計画する
施設のバリアフリーやユニバーサルデザインは後から増設したり、改修を行うと施設を全体でみた時に歪になり、改修費用もかかります。
構想や設計の段階から6つのポイントと共に障害者を含む当事者の意見を取り入れることで、余分な工程や費用を押さえ、バリアフリーやユニバーサルデザインに必要な要素を取り入れることができます。
障害者や高齢者を含むすべての方々が、友人や家族とともに観劇を楽しめる空間づくりの実現を、この機会に考えてみてはいかがでしょうか。
■改修が困難な建物でも、多様な方が訪れやすい施設へ 東京文化会館の事例
→https://www.mirairo.co.jp/works/portfolio/post-12508