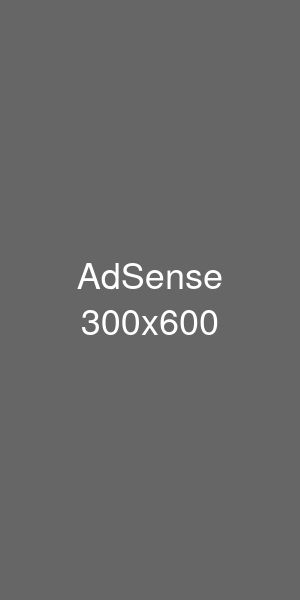「文字通訳」とは、話されている内容をリアルタイムで文字に変換して伝える通訳方法です。聴覚障害者や高齢者など、聴こえに困難がある方に対して、視覚的に情報を理解するための手段のひとつです。本記事では、文字通訳サービスについてご紹介いたします。ぜひ、ご覧ください。

目次
・文字通訳の変遷と多様な形態
・活用されている場面・事例
・文字通訳者の専門性について
・誰もが情報にアクセスできる社会へ
文字通訳の変遷と多様な形態
一口に「文字通訳」と言っても、その方法はさまざまです。要約筆記、音声認識文字通訳(たとえばUDトークの修正など)、字幕通訳など、多岐にわたる形態があります。そしてその発展は、電子機器の進歩と密接に関係してきました。
手書きによる要約筆記の時代
はじめは、筆談に近い形で紙に手書きする方法が主流でした。「ノートテイク」と呼ばれ、大学の講義などで対象者の隣に座り、話を要約しながら記述していく方法です。この場合、リアルタイムで文字化できるのは全体のおよそ2割程度と言われています。
OHP(オーバーヘッドプロジェクター)の登場
その後、プロジェクター機器の発展により「OHP(オーバーヘッドプロジェクター)」が登場します。手元の文字をスクリーンに映し出すことで、1人のテイカーがより多くの聴覚障害者に情報を伝えられるようになりました。
ただし、書く人の他にロール紙を調整する人、交替要員などが必要で、略語の使用など利用者側にも一定の知識が求められることがありました。現在ではOHPはあまり見かけなくなりましたが、一部の自治体・団体では今も活用されています。
パソコン要約筆記の普及
近年、パソコンの普及により、伝えられる情報量は大幅に増加しました。手書きで伝えてきた情報をパソコンに入力することで、より多くの内容をリアルタイムで文字にすることが可能になりました。この「パソコン要約筆記(PCテイク)」では、一般的なPC利用者が1分あたり60〜100文字、事務職など速い人で120〜150文字程度のところ、文字通訳者は150〜180文字、あるいはそれ以上の驚異的なスピードで音声を文字化していきます。PCテイクの場合、音声情報の約6割程度を文字化できるとされています。
音声認識技術の進化と現在
さらに現在では、スマートフォンの普及とともに音声認識ソフトの活用が進んでいます。話された内容を自動的に文字に変換するアプリが多く登場し、誤変換の精度も年々向上しています。しかしながら、認識率は100%ではなく、リアルタイム修正が必要不可欠です。ここで重要な役割を担っているのが、文字通訳者による修正・整文作業です。最近は、「PC入力+音声認識+通訳者による修正」というハイブリッド型の情報保障が主流になりつつあります。

captilOnlineの利用者画面例
活用されている場面・事例
文字通訳は、イベントや会議、芸術関連など幅広い場面・分野で活用されています。
当社の文字通訳派遣サービスは、入社式、社内ミーティング、会議、懇親会、決起集会、演劇、決算説明会などの場面で多くの企業・自治体がご利用くださっています。
過去に一緒にお取り組みを行った実績をご紹介します。
●東武トップツアーズ株式会社
オンライン・フォーラムの運営にあたり、文字通訳派遣サービスをご活用いただきました。文字通訳者を1日合計20名配置し、聴覚障害者がすべてのフォーラムに参加できるように情報保障を整備されました。
●青山学院大学
大学のリアルタイム型オンライン授業、オンデマンド授業の情報保障に、文字通訳派遣サービスをご活用されました。大学や教員の皆さまの確認、ご協力により聴覚障害学生が授業へ参加できる環境を整備されました。
●吉本興業株式会社
「聴覚障害のある方やご高齢の方にもコンテンツを楽しんでもらいたい!」という担当者の想いを受け、映像配信サービス「FANY チャンネル」にて配信されている一部のコンテンツに、バリアフリー字幕を付けられました。単に音を全て文字化するのではなく「番組を楽しむために必要な情報を文字にする」バリアフリー字幕を作成されることで、より聴覚障害者が楽しめる環境を整備されました。
●フューチャー株式会社
社内の情報保障として、文字通訳派遣サービスをご活用いただいております。グループの定例ミーティングや新人研修などに情報保障をつけることで、聴覚障害のある従業員が主体的に参加できるようにし、働きやすい環境を整備しておられます。
また、年間通して派遣の契約をしているため、通訳者も専門用語に対応できるようになり、情報保障の質の向上にもつながっています。
●帝国劇場
聴覚障害者への情報保障として、演劇に文字通訳を導入いただきました。10日前までの申請で文字通訳をつけることができ、セリフ、歌、トークショーなどの音声情報を文字としてお届けしました。
そのほか、多くの企業・自治体などが文字通訳サービスを導入しています。
詳しくは、実績ページをご確認ください。
2024年4月に改正障害者差別解消法が施行されたことよって、民間事業者の障害者への合理的配慮提供が努力義務から法的義務へ移行したことにより、情報保障の重要性およびその認識は社会全体に浸透してきています。また、障害者の法定雇用率も2024年度に2.5%、2026年度に2.7%と段階的に引き上げられていることに伴い、企業内における情報保障のあり方も再考され、変革が進行しています。これらの社会的な背景から、文字通訳の需要は急速に増加しています。
文字通訳サービスについて詳しく知りたい方は、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
問い合わせフォーム
文字通訳者の専門性について
登録文字通訳者①
ミライロに登録させていただいてから、様々な現場を経験させていただいてきました。字幕を見て「こんなものか…」とがっかりされては、次回のご利用に繋がらないかもしれません。繰り返しご依頼いただくお仕事に対しても「油断」や「慣れ」が生じないように、できるだけの準備と緊張感を持って臨むようにしています。文字通訳はチームでの仕事です。周りの皆さんは上手な方ばかりなのでとても勉強になりますし、心強く感じています。終わったあとは自分の力不足に凹むことばかりですが「また一緒にやりたい」と思わせてくれる方々ばかりです。これからも、ミライロを通して、情報保障の一端を担っていけたら幸いです。
登録文字通訳者②
話し手の言葉をリアルタイムで文字にするパソコンでの文字通訳では、正確さや速さに加えて、話の流れやニュアンスをくみ取り、読み手にとって伝わりやすい表現にすることも大切です。情報を「伝わる言葉」として届けるために、文を整えたり、必要に応じて漢字をひらがなに変えたりすることもあります。一語一語の奥にある思いや感情が、文字を通して伝わるように。通訳の文字が、話し手と聞き手をつなぐ橋渡しとなることを願いながら、「声」を確かに届けることを心がけています。
文字通訳派遣コーディネーター※ミライロ社員
文字通訳は、手話を使わない聴覚障害者にとって大切な情報保障手段です。質の高い通訳のためには、主催者の皆さまのご協力(資料提供や通訳環境の整備、話し方の工夫など)が不可欠です。私たちコーディネーターは、通訳者が最大限の力を発揮できるよう、依頼者様との事前調整を丁寧に行っています。ミライロには、経験豊富で高い通訳技術を持つ通訳者がたくさん登録してくれています。現地・遠隔・全文入力・要約入力・音声認識結果の修正等、場面に応じた柔軟な対応が可能です。これからも、通訳者やご依頼者様と連携し、より良い通訳を提供してまいります。
誰もが情報にアクセスできる社会へ
改正障害者差別解消法により合理的配慮が努力義務から法的義務へと変わったことによって、情報保障の重要性や意識が浸透してきました。
また障害者の法定雇用率が上がっていることから、社内での情報保障の在り方が見直され変わりつつあります。聴覚障害者・ろう者への情報保障は手話だけではなく、文字もあり、これは高齢者にとっても有用なサポートとなります。
ミライロ・コネクトでは引き続き、さまざまな場面において文字で音声情報が得られる社会を目指します。どんな場面でも手話や文字による情報保障をご希望の方はどうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
ミライロ・コネクト事業
メール:connect@mirairo.co.jp