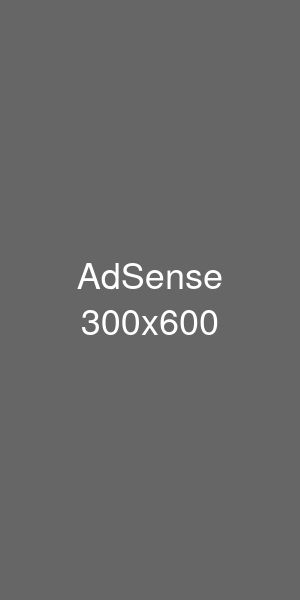新型コロナウイルスの感染拡大が問題視される中で、聴覚障害者や手話通訳者の濃厚接触を回避するためにも、遠隔における手話・文字での情報保障はとても重要です。
また、手話通訳者の中でも特に、手話通訳士の資格を持つ人は僅か3,822人と少なく、高齢化も問題とされています。
※ 社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター(2020年3月)
さらに、通訳者の数に限りのある地域も見受けられるため、新型コロナウイルスが収束した後においても、遠隔で通訳できる仕組みづくりは必要不可欠です。

聴覚障害者の現状
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、聴覚障害者の情報取得の難しさが、より際立ってきています。
例えば、話す人がマスクを着用することが増え、聴覚障害者が口話(唇を読み取って会話をする手法)でコミュニケーションをすることが難しくなりました。
マスクを外してほしいと伝えても、拒否されることもあります。
また行政からの報道発表がある際も、会場に手話通訳者が配置されなかったり、配置されていてもカメラアングルによりテレビに映されないことがあるため、聴覚障害者にその内容が伝わらないことが問題になっています。
その他、テレワークが推奨され、テレビ会議等も増える中で、多くの聴覚障害者が、業務上においてコミュニケーションの問題で困っています。
●テレビ会議では、口話が読み取れないため、会議に参加できない。
●聴者のスピードで会議は進行するが中断してはいけないと思い、なかなか言い出せない。
●手話通訳者や文字通訳者を派遣してもらえないので、情報保障がなく困っている。
※ミライロが実施した、「新型コロナウイルスによる影響」調査結果はこちら
|
|
手話通訳者の現状
手話通訳者もコロナウイルスの感染拡大に、大きな影響を受けています。
手話通訳を行う場合、基本的にマスクを着用することができません。
手話は、手だけではなく表情や口の動きが文法として、とても重要だからです。
同じ手の形でも、口の形が違うだけで全く違う意味になることがあります。
体の動き、顔の表情、口の動き、手の動きを複合的に使って手話通訳を行いますので、マスクで口元を隠すということは「聴覚障害者への情報伝達のバリア」に繋がるため、マスクは着用できないのです。
あらゆる場面においてマスクが着用できないことから感染のリスクが高くなり、特に病院等医療現場での通訳の場合には、通訳者も感染等のリスクがあります。
また、手話通訳者が聴覚障害者や医療従事者へ感染を広げてしまう危険性もあります。
そのような危険を伴いながら、情報保障を担う通訳者として、現在でも全国各地で多くの通訳者がマスクなしで医療関係の通訳を行っています。
遠隔での手話・文字通訳の仕方
そこで、手話や文字での情報保障を行う弊社の事業「ミライロ・コネクト」では、テレビ会議や面接に課題を感じている聴覚障害者へのサポートとして、遠隔での通訳を開始することになりました。
会議や採用活動、研修にオンライン会議システムを導入している企業に対し、遠隔での手話・文字通訳を提供します。
なお、ミライロでは原則として手話通訳者も自宅から通訳を行うことで、通訳者の感染リスク削減を目指します。

今後について
ミライロでは、これを機に「通訳手段の選択肢」を増やしていくことも目標とし、今後より聴覚障害者が暮らしやすい社会を築いていきます。
聴覚障害者への配慮を簡単にチェックできる便利なリストは以下のリンクからダウンロードください。
聴覚言語障害者への配慮に関する簡易チェックリスト
■通訳に関する依頼
通信状況により、遠隔での通訳が難しい可能性もございます。
下記のメールにお気軽にご相談くださいませ。
ミライロ・コネクト事業部 connect@mirairo.co.jp
HP https://mirairo-connect.jp/