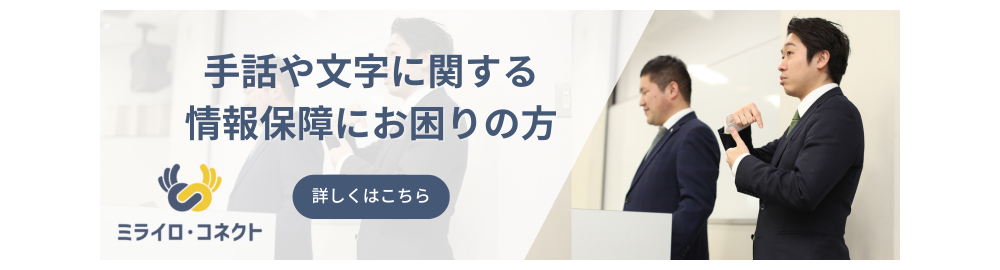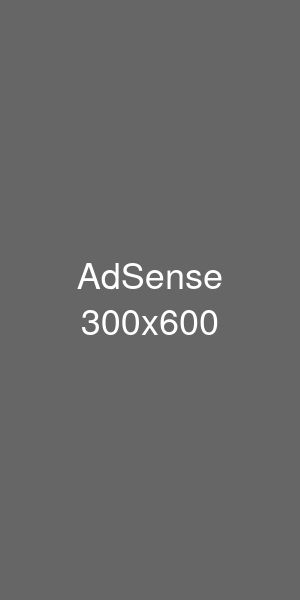*母語、第一言語に限らず手話を日常的に話す人を指す。
1.はじめに
ー アンケートの実施について(目的)
2.私生活・職場での使用言語のアンケート結果
ー 勤務先への要望と現状の課題
ー 職場で困っている場面
3.現状と求められる情報保障のアンケート結果
ー 利用傾向と導入意欲 ― 潜在需要の高さが示す導入の必然性―
ー 実際の声が語る「必要性」
4.まとめ
ー 遠隔手話通訳の可能性
アンケートの実施について(目的)
近年、聴覚障害のある方々への情報保障が少しずつ広がってきました。
しかし、職場や日常生活では依然として情報格差が存在し、特に手話を母語や第一言語とする人々などは、多くの課題に直面しています。会議や研修、緊急時の対応など、即座に情報が必要な場面で、情報が得られず、聞こえる人との間に大きな差が存在するのが実情です。
今回私たちは、手話話者を対象にアンケート調査を行い、勤務先やプライベートにおける情報保障の実態と、遠隔手話通訳サービスに対するニーズを調査しました。
※アンケート実施期間は、2025年6月1日~6月30日です。回答者数は133名。うち手話に関連する回答者は66名です。手話に関連する回答は、普段のコミュニケーションに手話を選択した方が回答しています。
勤務先への要望と現状の課題
職場で手話を使っているかのアンケート回答では、私生活と同様に職場でも手話を使えている人は約38%にとどまります。つまり、過半数以上が自らの母語や第一言語で働くことができておらず、日常的に情報取得や意思疎通で不利な立場に置かれています。
Q職場で手話を使っていますか?

さらに、業務において手話通訳を希望するかのアンケート回答では約73%にのぼる一方で、実際に手話通訳が導入されているかのアンケート回答では約26%にとどまりました。
Q業務において手話通訳を希望しますか?

Q実際に手話通訳が導入されていますか?

この結果は、制度や仕組み自体は存在しても、それが現場で十分に活用されていない現状を示しています。そのため、重要な情報が得られず会議や打ち合わせで誤解が生じたり、意図が正しく伝わらないといった不便が日常的に発生し、業務効率や生産性にも影響を与えています。
職場で困っている場面
職場で困りごとを感じる場面に関するアンケートでは最も多い33名から挙がったのは「社員・スタッフ同士のやり取り」(約50%)で、次に32名の「打ち合わせや面談(社外)」(約48%)が続きます。
Q職場で困りごとを感じる場面はどんな時ですか?

これらは突発的に発生することが多く、事前準備が難しいため、情報保障が間に合わない場面です。
一方、研修で困っていると答えた人は21人で約31%にとどまりました。研修のように事前に予定や内容がわかっている場面では、比較的情報保障が整っていることがうかがえます。
つまり現状では、「予定がある場面」には対応できても、「突発的に発生する場面」には対応が難しいという課題がわかりました。
利用傾向と導入意欲 ― 潜在需要の高さが示す導入の必然性―
遠隔手話通訳サービスの利用実態のアンケート回答では、私生活で遠隔手話通訳サービスを利用した経験がない人は約半数ですが、月1回以上利用している人が約14%、数か月に1回利用している人も約9%存在しています。
Q遠隔手話通訳サービスを利用したことがありますか?

この数字だけを見ると利用率は限定的に見えますが、職場での遠隔手話通訳サービスの利用意向に関するアンケート回答を見ると、約75%の人が「使いたい」と答えており、需要の高さを示しています。また「どちらともいえない」と答えた方からは、「現状Wi-Fi環境の整備が不十分である」や「手話通訳者に実際来てもらいたい」、「動き回るため端末を持ち運べるのであれば使いたい」といった声が寄せられました。つまり、利用実態と需要は反比例しており、単に需要がないのではなく、「利用環境が整っていない」という大きな障壁があることがわかります。
Q遠隔手話通訳サービスを利用したいですか?

さらに「ぜひ使いたい」と答えた方の多くが、「雑談でも通訳をつかえたらいい」と回答しています。聴覚障害者にとって、仕事に必要な情報が共有されるように整備されてきたと感じるも、聴者同士の世間話には入ることができず、疎外感を感じるという声は多く上がっています。
こうした声は、遠隔手話通訳サービスを有効な解決策として期待している人が多数いることを明確に示しているといえます。
実際に、遠隔手話通訳サービスを導入されている企業では、聴覚障害のあるお客様への対応時、筆談や身振りでやり取りを行っていましたが、商品の説明や契約手続きに時間がかかり、お客様にもスタッフにも負担となっていました。
導入後は、タブレット越しに手話通訳者と即時につながることで、説明がスムーズになり、1回あたりの接客時間が短縮され、待ち時間も減り、混雑時の回転率向上にもつながりました。さらに、利用したお客様からは「こんなにスムーズに説明を受けられたのは初めて」「安心して質問できた」といった声が寄せられました。店舗スタッフからも「接客のハードルが下がり、もっと提案できるようになった」と好評です。
実際の声が語る「必要性」
自由記述には、導入の直接的な要望や具体的な活用イメージが多数寄せられました。
「当社に限らず、遠隔手話通訳を必須にしてほしい」
「導入事例がないので、メリットとデメリットを説明して導入を促してほしい」
「社外の研修や打ち合わせのために、気軽に使える遠隔通訳がほしい」
「緊急時にも即時対応できる仕組みが必要」
「手話+文字テキストがあれば誤解を防げる」
こうした声から見えてくるのは、遠隔手話通訳は単なる便利ツールではなく、安全性と業務効率を支えるインフラであるという事実です。
遠隔手話通訳の可能性と社内での情報保障の充実を
今回の調査では、「必要性が低いから使われていない」のではなく、「環境が整っていないため、十分に活用できていない」という現状が見えてきました。
多くの方が利用を望んでおり、改善すべきポイントもはっきりしています。つまり、導入に向けた土壌はすでに整っていると言えるでしょう。
遠隔手話通訳サービスがあれば、会議や研修での情報共有がスムーズになり、災害や緊急時にも安心して行動できます。さらに、誰もが同じ情報にアクセスできることは、企業が取り組むダイバーシティやインクルージョンの推進にもつながります。
自由記述でも、「ぜひ導入してほしい」「社外対応のために必要」という声が多く寄せられました。これらの声は、日々の安心や業務の効率化に直結する具体的なニーズです。
遠隔手話通訳サービスは、情報の壁を低くし、誰もが安心して働き、暮らせる社会に近づくための大切な一歩です。
ミライロ・コネクトでは、これからも手話や文字によるコミュニケーションが自然に行える社会を目指し、さまざまな場面でのサポートを続けていきます。株主総会などで情報保障をご希望の際は、どうぞお気軽にご相談ください。