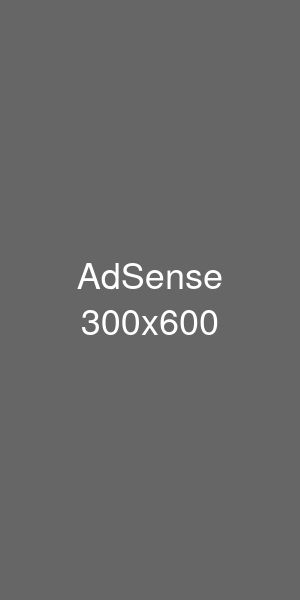目次
・はじめに
・聴覚障害者への情報保障に関するアンケート結果
・エンタメ分野において求められる、情報保障対応とは?
・まとめ
はじめに
情報保障に関する企業の対応について、業界別にお届けします。聴覚障害者へのアンケート結果とともにお伝えしますので、どのように情報保障を取り入れたらよいのかお悩みの方や検討されている方は、ぜひご一読ください。
第6回では「エンタメ分野」への情報保障 (例:演劇・音楽ライブ・お笑い・企業主催の展示会など)への情報保障についてご紹介します。
※第1回記事「聴覚障害者を取り巻く状況の変化と、企業に求められること」
※第2回記事「水族館・動物園など」に求める情報保障
※第3回記事「旅行・交通など」に求める情報保障
※第4回記事「美術館・科学館・博物館など」に求める情報保障
※第5回記事「イベントなど」に求める情報保障
以下は、116名の聴覚障害者に聞いたアンケート結果です。
聴覚障害者への情報保障に関するアンケートの結果
Q聴覚障害者に「エンタメ分野など」への情報保障(例:演劇・音楽ライブ・お笑いなど)があれば、どう思いますか?
.png?width=650&height=433&name=6th_graph01%20(1).png)
以上のように、61.2%の人が情報保障があれば嬉しいと答えています。一方で、約20%の方から行くこと自体がないという回答が寄せられました。
今の社会の中で、エンタメ分野の場面で聴覚障害者が楽しめるための情報保障(手話通訳・文字通訳など)がほとんどないため、聞こえない自分が行っても内容がわからない。だから、つまらないから行かないという方が多いのではないかと思われます。
では、聴覚障害者にとってどのような情報保障や合理的配慮があれば、行ってみたい魅力的な舞台やライブになるのでしょうか?
Qどのような情報保障があると嬉しいと思いますか?
芸人さんやタレントさんの会話の内容が、字幕でステージ横のスクリーンなどに即時反映されるシステムがあればうれしい。
リアルタイムで漫才の内容を手話で表してくれると一緒に笑えると思う。
手話通訳や、歌詞(どこを歌ってるか色つける)や内容を字幕で出してくれると嬉しい。特に推しのMCを聞いてみたい。
字幕などがあると、補聴器をつけても聞き取れない言葉をすべて漏れなく理解できて、楽しめる。
歌舞伎や能などの伝統芸能を鑑賞した経験がないため、情報保障つきで鑑賞してみたい。
とのご意見があります。
エンタメ分野において求められる、情報保障対応とは?
現状では情報保障がないため、残念に思っている例として下記のようなエピソードをご紹介します。
ある聴覚障害者は、球場にも応援に行くくらいプロ野球が大好きで、ひいきにしているチームがあります。チームが勝つともちろん嬉しいのですが、残念なことが一つだけあります。それは、ヒーローインタビューの内容がわからないことです。周りのみんなが選手の声に盛り上がっても、何を言っているのかはその場ではわからず、家に帰ってスポーツニュースの字幕を見て、初めて何を話していたのかがわかるというのです。
他にも、演劇には興味があり生で見てみたいが、字幕がないのでセリフがわからないから行かず、テレビで我慢している方もおられます。でも、舞台やステージなど、生ならではの臨場感や音の響き(音の振動を体で感じたり、補聴器等で音がわかる聴覚障害者もおられます)、会場の熱気、スターや推しの表情を見て感じられることがあります。その楽しみを十分に満喫できないため、行きたい気持ちも萎えてしまうという方もおられるのです。
また、現場での対応についても配慮が必要になります。
このようなご意見もありました。
観劇で、セリフがわかるシナリオを見れるよう、タブレットを用意してもらった。それが許可のない撮影や録音をしているわけではないことをスタッフが周りの客に説明をした。その際、自分の障害の話などもされ、知らない人に個人情報を晒されるようで気持ちの良いものではなかった。
ご自身の障害について、第三者から勝手に説明をされるのがイヤだと思われる方や、周りからの理解を得るためなら全然気にしないから言ってほしいと考える方など、お考えはみなさんそれぞれ異なります。
こちらが考えた配慮を気持ちよく受けていただくためには、「周りの方にこのようにご説明しても良いですか?」と一言確認をすると、より丁寧な対応になるでしょう。あっさりと「いいよ」と言っていただけるかもしれませんし、もしかしたら、もっと良い伝え方があるとご自身の経験から別のアイデアを教えてくださるかもしれません。
合理的配慮とは、「こちらが考えた画一的な配慮を提供する」のではなく、お客さまが望むことと主催者である企業側ができることを出し合って、無理のない範囲で歩み寄ることなのです。どちらかの意見を一方的に押し付けるのではなく、まず、建設的なコミュニケーションをとることから始めてください。
もしかしたら、今回は「できなかった」と残念な結果に終わってしまうかもしれませんが、お互いの気持ちを知ることができると納得感が違いますし、将来的によりよい状況に変えていくきっかけにも繋がります。
それこそが、お客さまに「また来よう!」と思っていただき、主催者の皆さまの「すべてのお客さまの満足に近づけるように」との願いが一歩ずつ進むという意味ではないでしょうか。
他に自社の工夫でできる対応としては下記のことが挙げられます。
歌詞を、文字で出せるように舞台や舞台袖にスクリーンなどを用意する。
受付では、コミュニケーションボードなど、指差しで確認ができるものを用意する。
筆談の準備をする。
演劇などのシナリオを事前に見てもらえるように、希望があればお渡しする。
では、聴覚障害者が芸能関係で楽しんでもらうためにはどのような情報保障があればよいのかご紹介をさせていただきます。
イベントでは手話通訳や文字通訳を準備する。
コンサートなどのMC部分は、手話通訳や要約筆記を配置する。
窓口や座席案内などの担当者のために、手話講座を開催する。
まとめ
現在、手話通訳や要約筆記or文字情報付きの観劇は、一部で行われています。演劇は、演者も練習をするように、手話通訳も練習が必要になります。そのためには、事前にシナリオを通訳者へ提供し、できれば練習やリハーサルにも通訳者が同席できる機会を設けていただけると、より質の高い通訳を提供することができます。
まだ数は少ないですが、実際に練習も一緒にし、手話表現が難しいところなどがあれば、ニュアンスを演者や演出家に確認をしてよりわかりやすい手話表現を工夫をするなどの取り組みも始まっています。
また、お笑いライブなどでは、テンポなどもあり、スピードについていくことはとても難易度が高くなります。これらも、事前にどのような話かを通訳にお伝えいただけると、通訳をしやすくなります。
難しい通訳現場ではありますが、聴覚障害者の希望があれば、今後は芸能に関する内容にも挑戦していくことが望まれます。まだまだ現場の数も少ないですので、通訳者も経験が少なく、今後さらに発展していく余地が残っている分野です。
これは、手話通訳者や文字通訳者だけの努力では限界があり、主催者や実際に舞台に立つ方たちの協力が不可欠で、協働していくことでより良い舞台につながっていきます。なにから始めればよいのかわからないなど、気になることがあれば是非ご連絡ください。
今回のアンケートの結果からもわかるように、聴覚障害があるお客さまからの情報保障へのニーズは高く、2024年4月の改正障害者差別解消法の施行により、民間事業者の障害者への合理的配慮提供が法的義務化されたことをふまえて各企業から、現地または遠隔による手話通訳や文字通訳のご依頼、業務上使える手話講座のご相談をいただく機会が増えています。
ミライロ・コネクトでは引き続き、さまざまな場面において手話でコミュニケーションがとれる社会を目指します。手話講座をご希望の方はどうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
ミライロ・コネクト事業
メール:connect@mirairo.co.jp